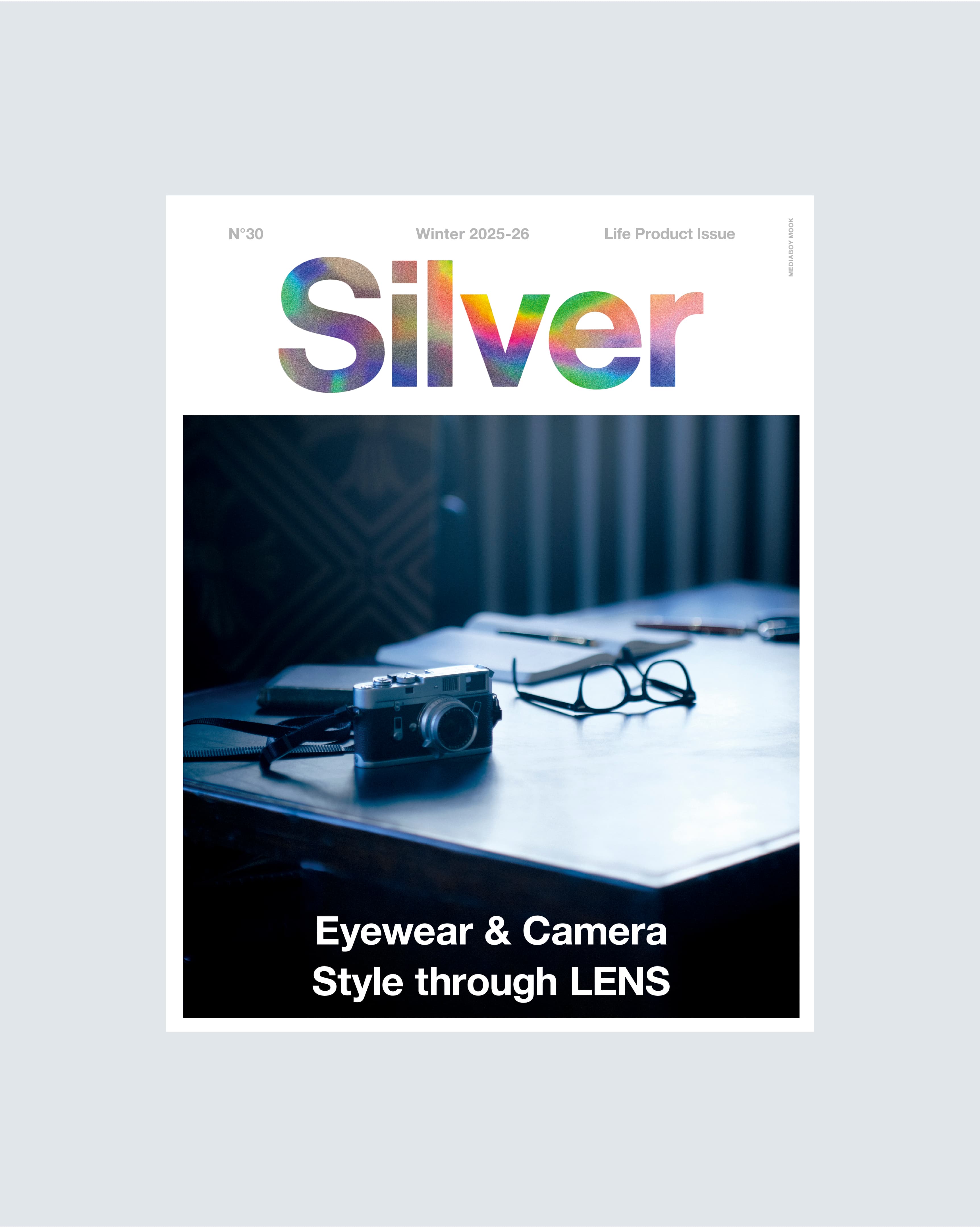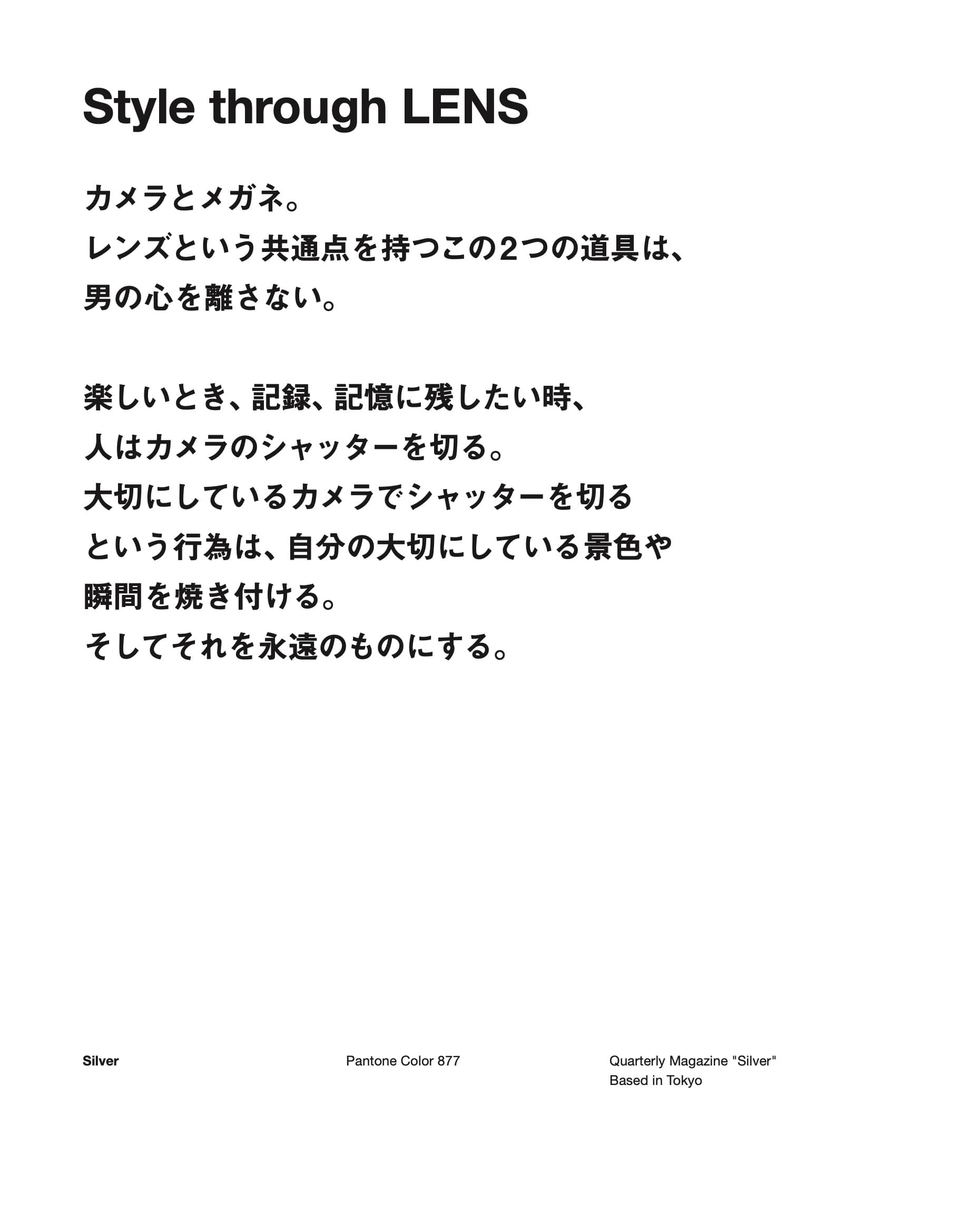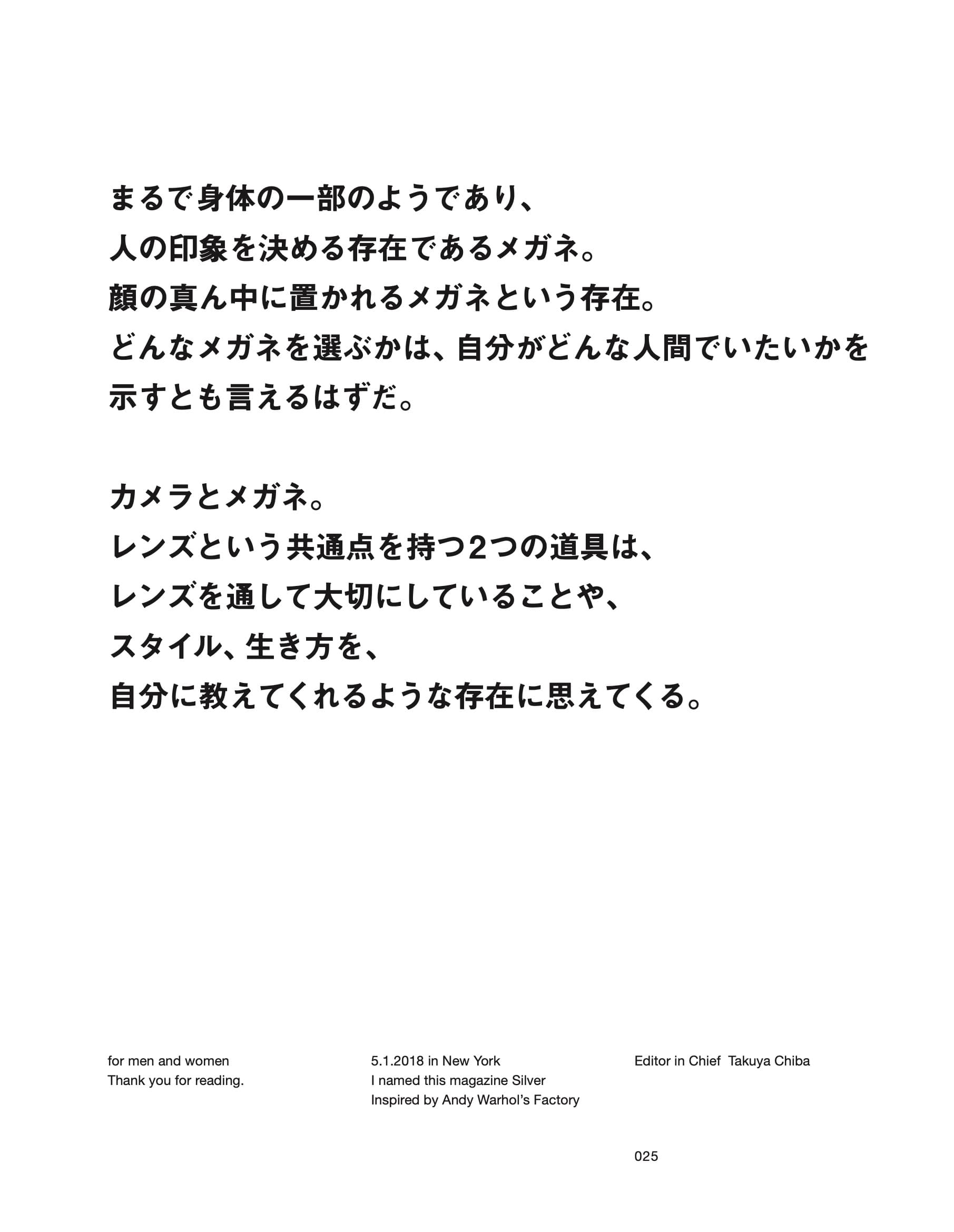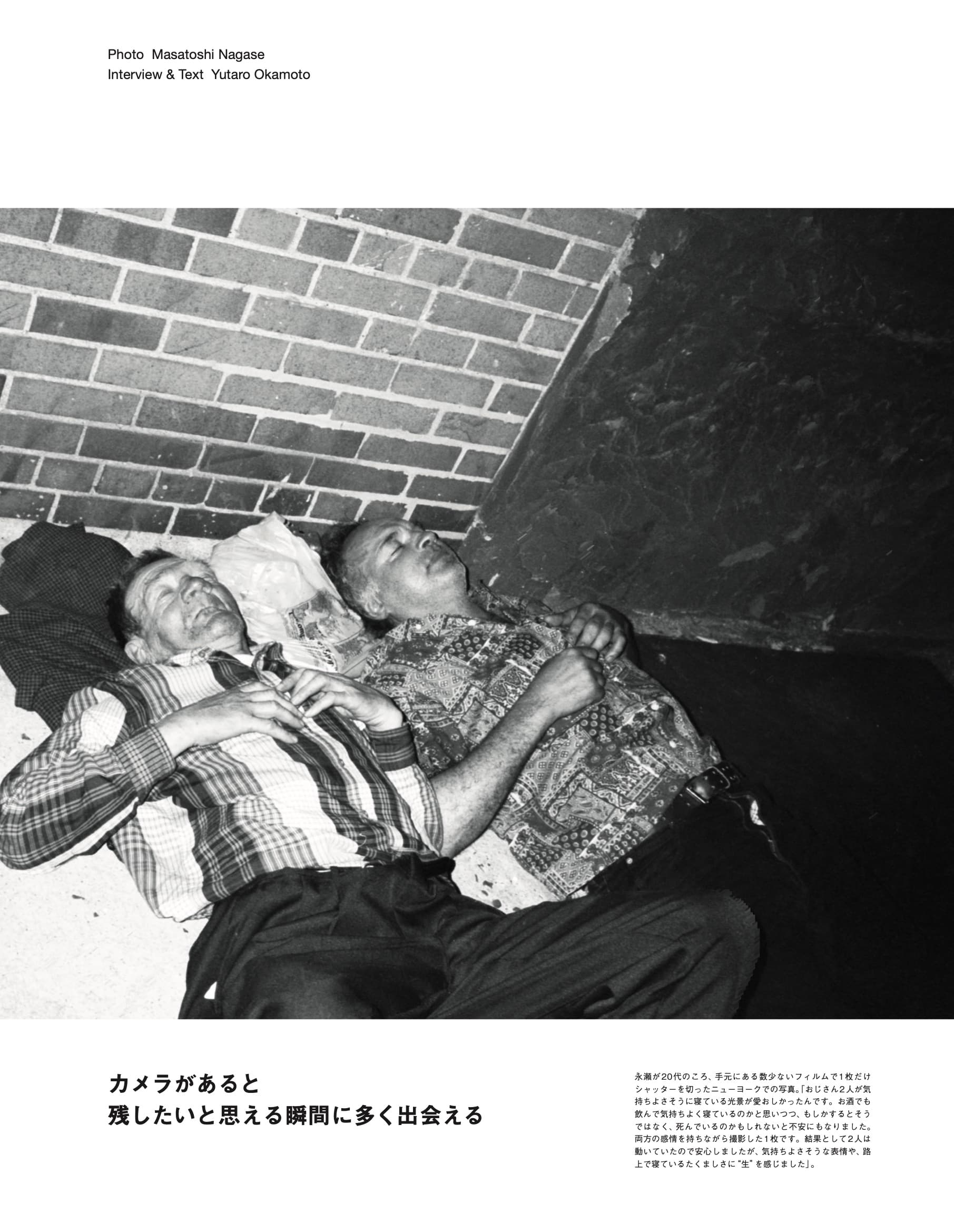Interview with Andrew Bunney (BUNNEY)
英国のユースカルチャーを世界へ届ける ジュエリーの域を超えたクリエイティブ

名だたるストリートブランドでデザイナーやクリエイティブディレクターを務めたのち、自身の名を冠したジュエリーブランドBUNNEYを創業したアンドリュー・バニー。彼のクリエイティブはジュエリーの枠だけにとどまることなく、定期的に発刊しているフリーペーパーは今回で4号目を迎えた。新聞の体をなしながら、ブランド名の響きやアイコンとの結びつきを感じるテーマで発行された『The Rabbit』の発刊を記念し、渋谷PARCOでポップアップショップが開催中だ。彼のクリエイティブの根源を辿るため、来日したデザイナーのアンドリューに話を聞いた。
一つのトピックを深掘りすると
壮大なテーマへと繋がる
フリーペーパーを作りはじめた当初、忘れられてしまった写真家や過小評価され光を当てられてこなかった写真家にフォーカスし、『Selected Works』というテーマの元で彼らの作品をキュレーションすることを目的にしていたというアンドリュー。70年代から80年代までストリートで写真を撮ってきた写真家たちをフィーチャーしていた中で、エキセントリックな作風で知られる映画監督のケン・ラッセルも第二号で焦点を当てられた一人であった。彼は映画を撮り始める前、写真家として活動していたのだ。イギリスのユースカルチャーといえば、言わずもがなパンクが代表的なものであるが、そのアイコニックな存在であったのがテディ・ボーイたち。不良少年のような彼らのやさぐれた装いを模倣したテディ・ガールも、その影に潜むように第二次世界大戦後の爆撃跡地を溜まり場にして存在していた。ケン・ラッセルはテディ・ガールを写真に収めていて、その希少性とインパクトがアンドリューの胸を打ったのである。
しかし、第三号では写真家にフォーカスしながらも考え方を大きく変えて『The Badge』というタイトルで、BUNNEYのアイコニックなアイテムであるバッジの歴史を掘り下げた。土の中から発掘された1000年以上前に作られたと推測されるバッジから、現代で作られたものまで幅広くピックアップ。藤原ヒロシやUNDERCOVER の高橋盾、 WTAPSの西山徹らとコラボレーションした特別なバッジも制作され、日本をはじめとする各国でエキシビジョンが開催された。では最新号となる『The Rabbit』のテーマはどのように選定されたのか。
「バッジの号を作成した経験から、一つのトピックを深掘りすることに面白さを感じたんです。さまざまな視点から掘り下げてより多くのことを知っていく中で、そのテーマが日常的なものだったとしてもとても大きなテーマに仕上げていくことができる。たとえば、シド・ヴィシャスを通じてうさぎのことについて考えてみたり(シドが首につけていた南京錠を制作していた工場が「ラビット」という名前であった)、世界中で愛されているミッフィーというキャラクターを改めて調べたり。関係性が無いように見えてもうさぎという共通点で結ばれていて、一つひとつを深く知っていくことでそのテーマが壮大なものになっていくんです」。

そう話し、アンドリューは新聞をめくりながらページごとにどのような切り口でうさぎというテーマを掘り下げているのか教えてくれた。実際に載っている題材は私たちの日常に馴染んでいるものから、全く知る機会のなかったもの、知っていたはずなのにうさぎとの共通項を見出せないものまで幅広い。
「題材をピックアップするにあたって最もシンプルな方法は、時間の流れを追っていくこと。ピーター・ハントに歴史を聞くと、2000年前のローマ時代にまで遡りました。ローマ人にとってうさぎは肉を食べ、毛皮を靴に仕立て上げることができる非常に有益な動物だったんだとか。そういった歴史からスタートして現代までを辿る中で、私たちがカルチャーとして純粋に魅力的だと感じた事象をピックアップしています。その過程の中で、うさぎという動物が、人によってはすごく魅力的で特別な存在になりうることを理解しました」。
そう話すアンドリューは歴史上で最もうさぎについて多角的な視点で深掘りし、多くを知っている人物であると私たちに確信させた。それはきっと彼自身が本当に一つひとつの内容に面白さを感じて愛を持っているからで、『The Rabbit』という新聞がそれをまっすぐな形でまとめたものであるからだろう。ではブランド名、そして彼の姓である“BUNNEY”は、うさぎを意味する英単語である“BUNNY”とどのように結びつくのか。
「さまざまな企業でデザインを経験し、自分のブランドを立ち上げることになった時に、ブランド名を考えるのには長い時間がかかりました。その言葉の持つ意味や響きを考えたくさんの候補が浮かびましたが、やはり自分の名前をブランド名にすることがものづくりをする人間として一番正直であるように感じたし、聞こえ方もよかった。そして、ブランドのアイコニックなモチーフを何にしようかと考えた時に、音が同じということもあり自然な流れでうさぎを選びました。正直であることは、ブランドとしても一人のクリエイターとしても、ずっと大事にしていることなのです」。

正直さを大事にしながらクリエイションを続けていきたいと語るアンドリュー。ではジュエリーデザイナーであるはずの彼が、フリーペーパーという形式にこだわりを持ち、時間と労力を費やす原動力はどこから来ているのだろうか。
「どんな形式のクリエイティブにおいても、スペシャルで希少性が高いものを作り出し、世界中とコミュニケーションして発信していきたいと思っています。たとえば、第三号でテーマにしたバッジはいたって地味なものですが、人から人へ授与されることや時を超えて受け継がれていくことがあり、そこには大きな意味が発生しているのです。そういった形で、プレシャスなものを分野の垣根をこえてコミュニケーションしていきたい、というのが、フリーペーパーを作る理由です」。


正直で純粋で、個性があるものを
作り続けていきたい
もの自体の価値を追求することにとどまらず、それらがどのように人を介在して伝播していき、後世に残っていくかという過程にロマンを見出す。その姿勢は彼自身が作り上げるプロダクトだけでなく、彼が他のクリエイターとコミュニケーションを生み出すモチベーションにもつながっている。それこそが今回のポップアップでも店頭に並ぶCarhartt WIPやPORTERとのコラボレーションアイテムの制作の背景だ。
「コラボレーションしたいと思う相手は、その分野においてのベストな方々たちです。それは必ずしも最も高価であるという意味ではなくて、正直で純粋で、唯一無二の個性があること。これらは私がブランドとしてクリエイションを続けていく中でずっと大事にしているものでもあります。
今回新聞という形で『The Rabbit』を発刊し、イギリスの街中や地下鉄で実際にジャーナルが売られているようにキオスクのような場で発表したいと思いました。キオスクでお土産を購入しようと思った時に個人的に欲しいのはトートバッグとTシャツ。そう考えた時に、それぞれの分野で最もクラシックで正直な存在である2社とコラボレーションできたことは、とても幸運なことだと思っています」。


正直さと純粋さ、そして個性を持つことこそがクリエイティブの真髄であるという考えのもと、ジャンルの垣根を超えて新しいものを生み出し続ける。ではそういったクリエイションは、ブランドの軸であるジュエリーそのものとどのように相互に作用していくのだろうか。
「今回作った新聞は『Financial Times』という経済誌と同じ印刷所で印刷をしているのですが、一部ずつちょっとしたズレが発生していて手触り感が違うんです。それぞれに個性があるんですが、それこそが私がものづくりをする中で大切にしたいもの。実際にジュエリーを手に取った人には、良い意味での違和感を覚えて欲しいと思っているんです。
たとえば、アメリカで作られたものはジーンズに代表されるように、素材においても製法においてもタフで耐久性があるものが多いですよね。フランスのクリエイティブはその真逆で、ラグジュアリーファッションからも料理からもわかるように、デリケートな手作業が特徴です。これは私の考えですが、イギリスはその中間に位置していて、スマートな見た目でありながら、繊細すぎるわけでもなくある程度の強度も両立していると思うのです。金属を使ったものづくりに長い歴史のあるイギリスでジュエリーブランドを続けるのであれば、手に取った人にイギリスならではの空気感と特別なアイデンティティを感じてもらえるものを作りたい。願わくば、手に取る人の個性と相乗効果を持って深い意味を持つものとして時間を経るものであって欲しいです」。
メイド イン イングランドにこだわり続ける理由と、ブランドとしての理想を語ってくれたアンドリュー。彼らしく正直なものづくりで歴史を重ねながら、ジュエリーブランドとしてはどのような未来を描いているのか、今後の展望を聞いた。
「ジュエリーは人生の転機を記念し花を添える意味を持つもの。人と人の関係性の節目で贈り合い、時間が経ってそのジュエリーを見れば特別な場面を思い出したり、そうでない瞬間でも自分自身を特別な存在だと感じられるようなジュエリーを作り続けていたい。手に取った人にそう思っていただけていると嬉しいです。ほかのプロジェクトに関しても有機的な形で、自然に発展していけたらいいと思います。自分たちの作品を届けた誰かが、特別な気持ちになっていることを願います」。
アンドリュー・バニー
Gimme5、Stussy、NIKE、Dr. Martensでデザイナー、クリエイティブディレクターとしてキャリアを積み、2009年に自身の姓を冠したジュエリーブランドBUNNEYを創立。ロンドンの熟練した職人による手作業にこだわりながら、遊び心溢れた製品を生み出し続けている。
| Photo Yota Hoshi | Edit Katsuya Kondo | Interview&Text Aya Sato |