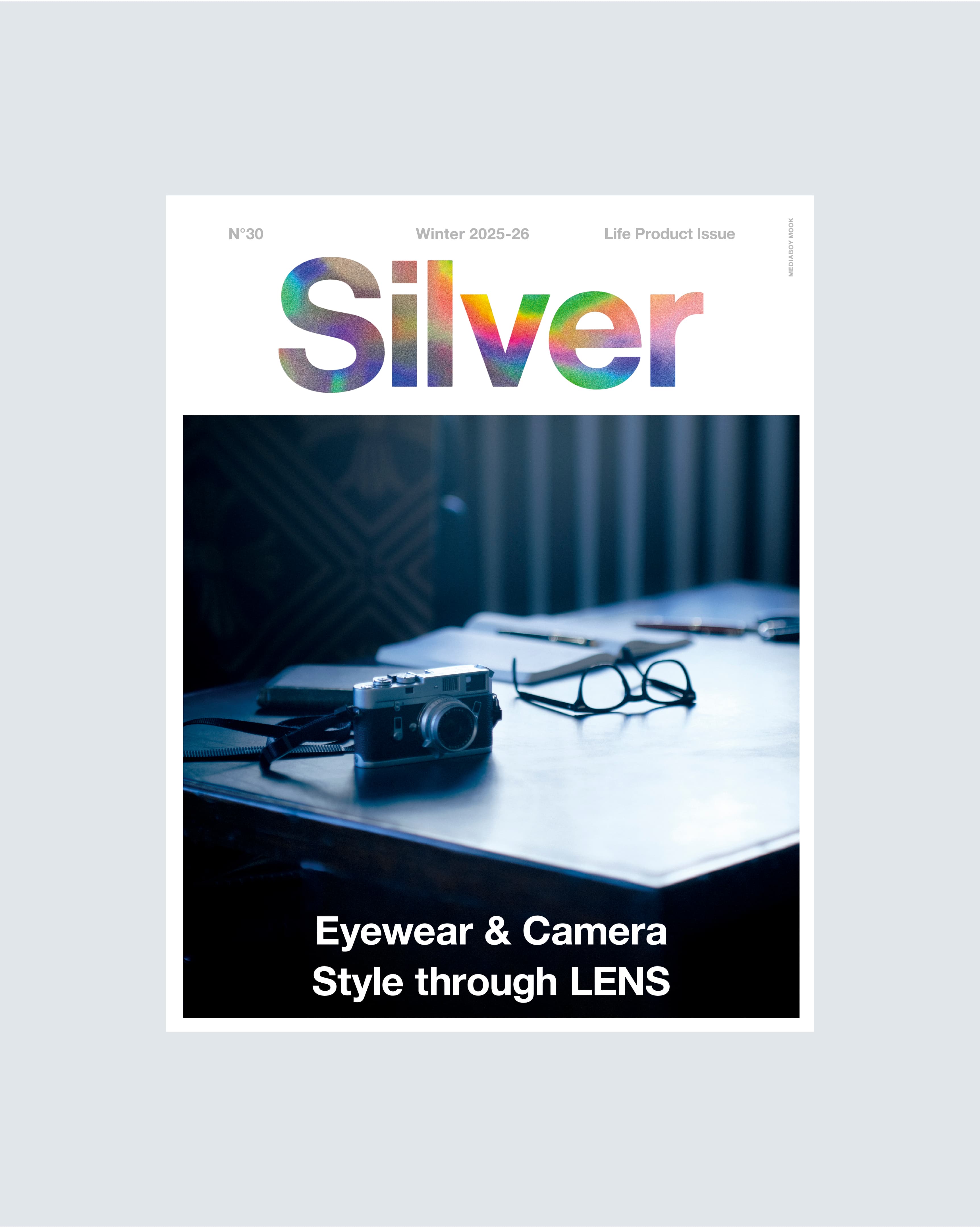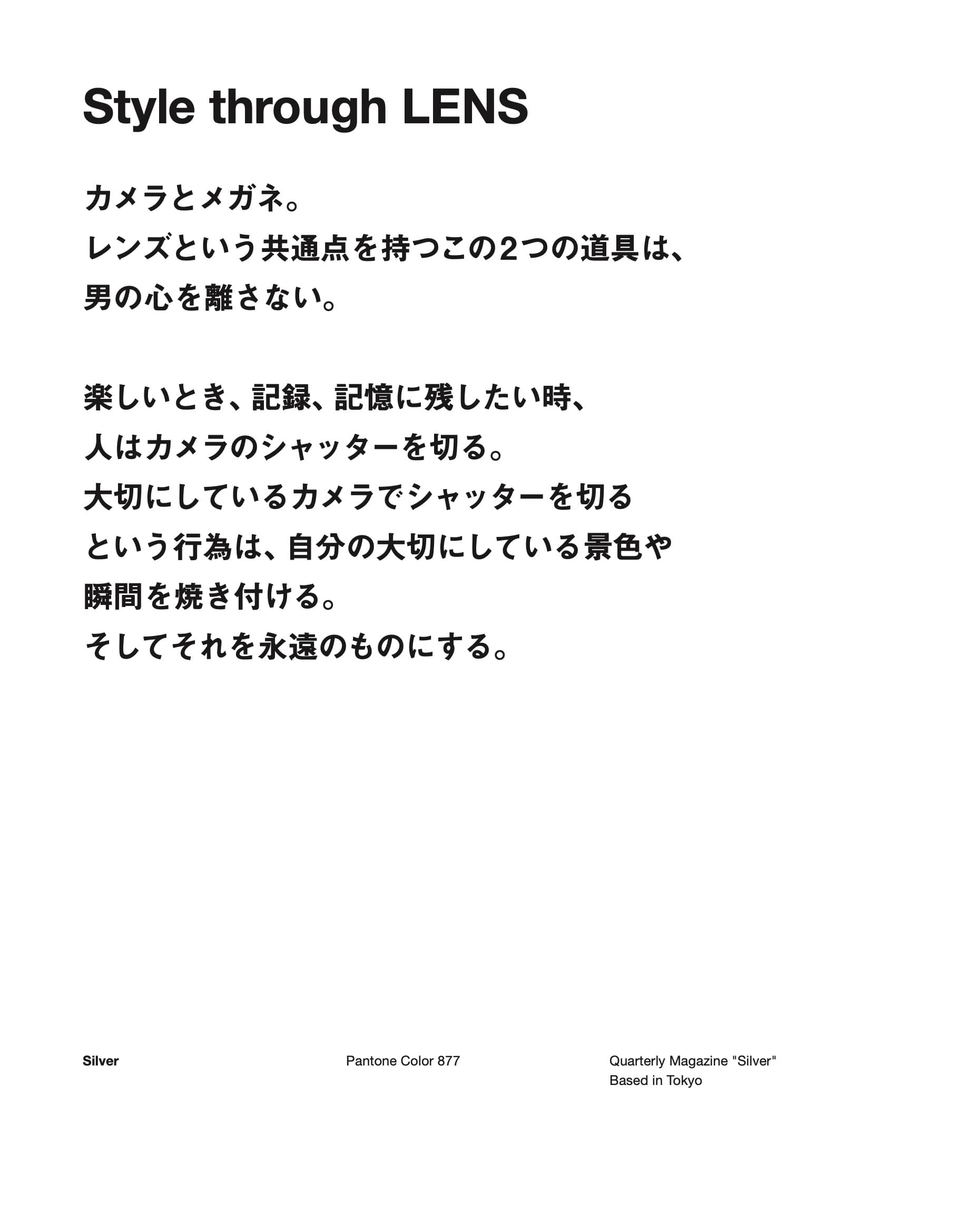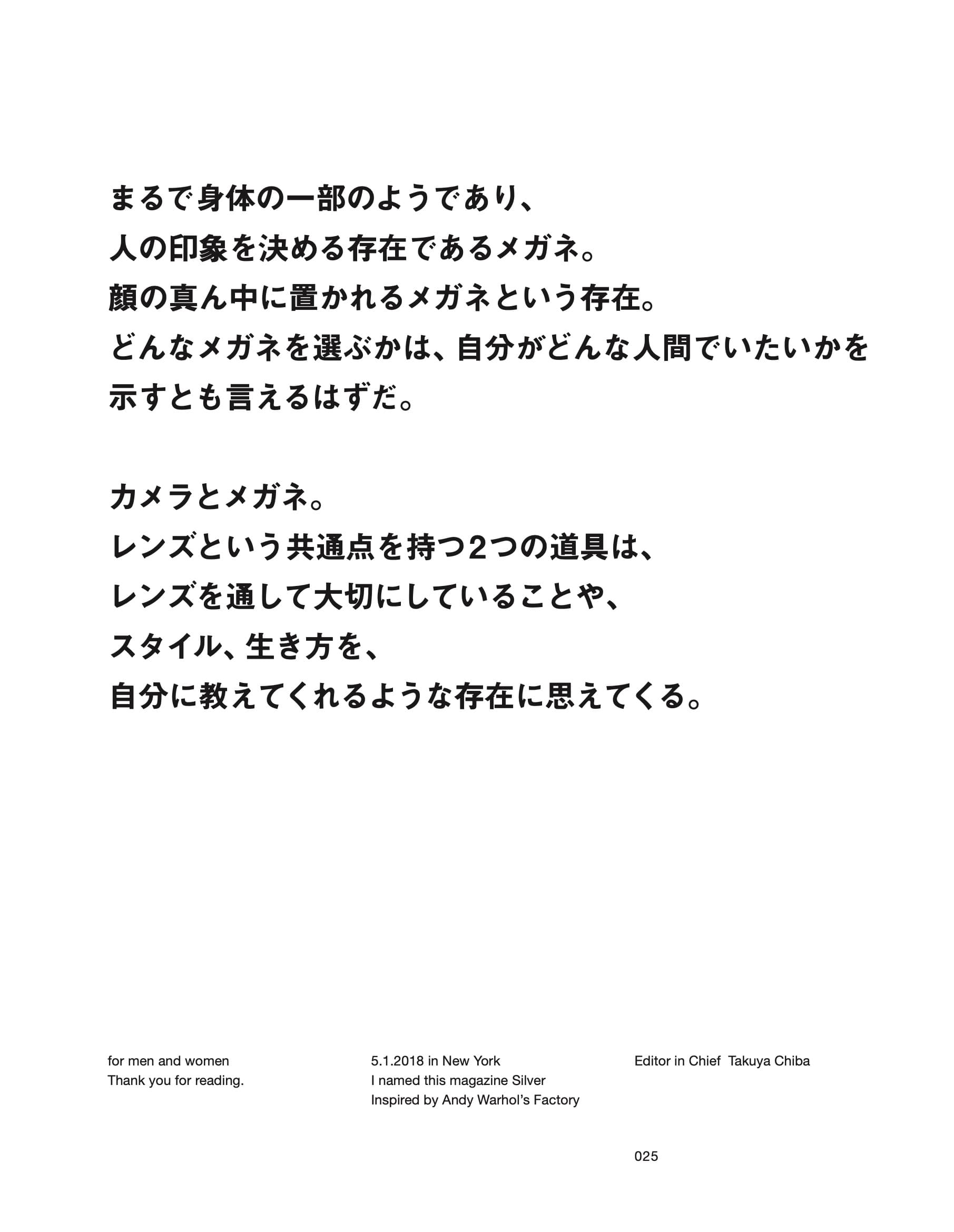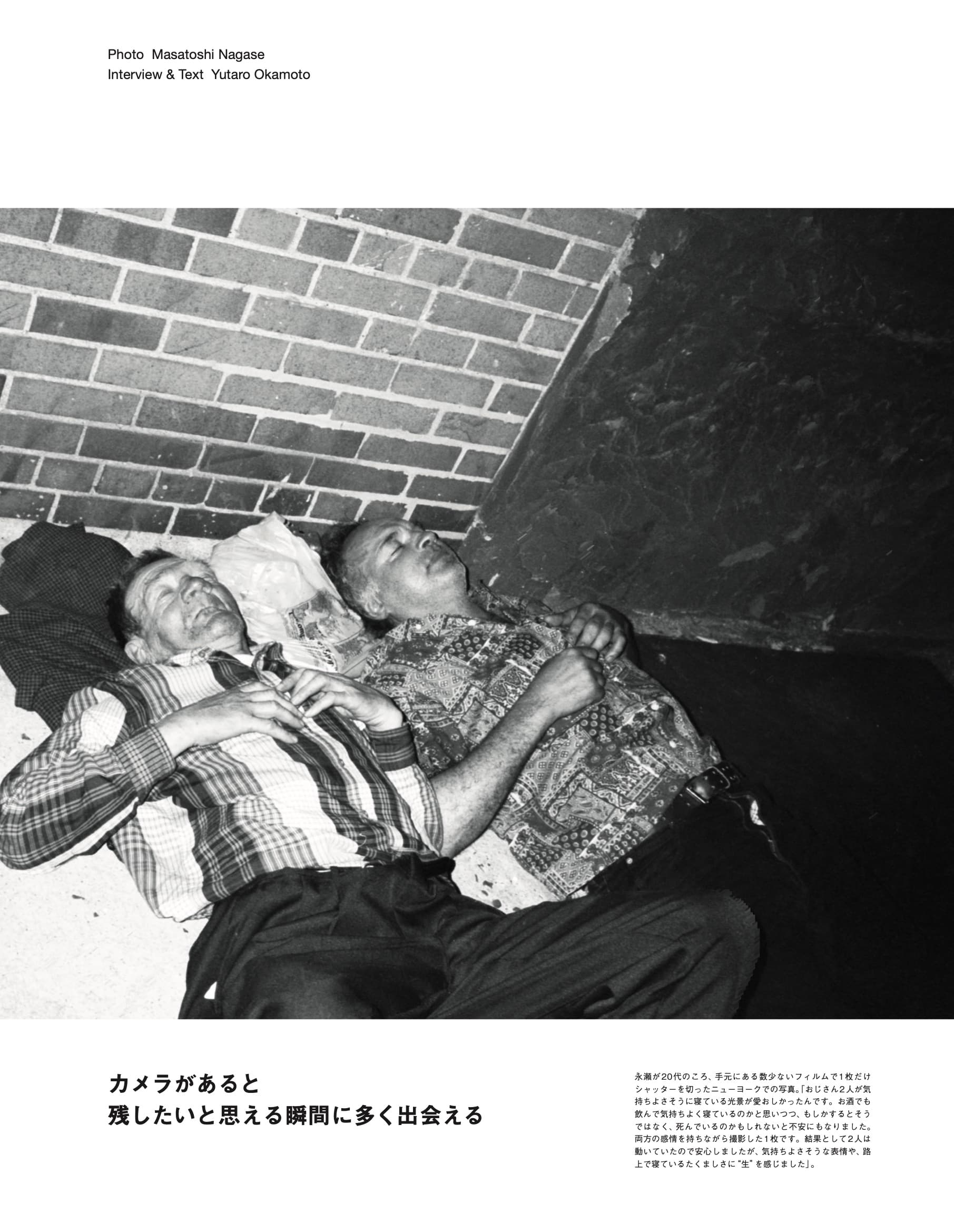Interview with Keita Motoji (Ginza Motoji)
人の手がどれだけ関わっているかが 受け継がれていくモノの条件

伝統や技術を絶やさないために
伝統の技術が息づく日本各地の産地で紡ぎ出される反物と、それらを仕立てた着物。こと日本文化において、その存在自体が受け継がれるヘリテージと言えるだろう。現代社会において着用の機会は減ってはいるものの、日本人として忘れてはならない精神のひとつだ。そんな日本のファッションにおけるヘリテージ的な存在としての着物という文化に、一石を投じ続けている人物がいる。呉服屋、銀座もとじの二代目、泉二啓太だ。大学時代をロンドンで過ごし、世界最先端のファッションを学んでいたという、呉服屋としては異色の経歴を持つ泉二。彼だからこそ見える、着物の新たな可能性を探る。
「時代を超えて受け継がれるものというのは、人の手がどれだけ関わっているかということが最も重要な要素であると思います。反物は製品として世に出るまでに非常に多くの人が関わっているものでもあります。その方々の多くはスポットライトが当たらない存在ではあるけれど、それぞれの伝統技術を一点一点の反物に結集させている。そうして誕生したプロダクトこそ時代を超えて受け継がれる要素を持っているんだと思います。特に着物においては、経年美化という考え方が重要で、使えば使うほど味が出てくるんです。着物で言うところの風合いのことで、50年、100年と受け継いで着続けていくことで生地の輝きが増していくんです。一番わかりやすい例で言えば、2000年の歴史を持つ結城紬(ゆうきつむぎ)という生地があります。元々は丁稚奉公に新しい状態の結城紬を着せて生地が柔らかくなってから主人が着るという文化がありました。素材は真綿なので、最初は光沢がなくほっこりとした質感なのですが、着れば着るほど毛羽立ちが取れ絹本来の持つ輝きが出てくる。これがもっと何十年、何百年着ていくことで更に光沢が増してきて非常に美しい着物になるんですよね。僕自身も譲り受けている一つの紬があって、日常的に数多くの着物に袖を通していますが、その着物だけは格別。日本工芸の持つ力を思い知らされます。着物自体にも時代を超えて受け継いでいくという性質がそもそも備わっているんです」。
脈々と続いてきた日本文化の中で、現在まで継承されている反物製造の技術や日本古来のユニークな柄などは、縮小の一途をたどっている。泉二はそんな現在の状況を改善するべく、さまざまな試みをおこなっている。
「日本各地、それぞれの産地で反物づくりに対する姿勢は大きく異なります。その土地の風土や生活水準によって使われる素材などにも影響が出るんです。先ほど紹介した紬でいえば、元々質素を尊ぶ武士に愛されていたものでした。江戸時代は贅沢禁止令が制定されていた時代でしたから、煌びやかな着物というのはなかなか難しい時代でもあった。一時期は光沢感のない紬の着用だけが許されて製造が盛り上がっていったという時代背景があるんです。ですが今や日本も洋服が装いの主流となっている世の中。需要と供給のバランスが当時と比べて大きく異なっている中で、作り手の方達がこれから先も続けていくことが難しい状況が続いています。断腸の思いで閉業してしまった方達も多く見てきた中で、この素晴らしい文化を絶やしてはならないと、反物の復刻を目指すことにしたんです。産地に実際に赴き、大正から昭和初期に流行した膨大な数の柄見本のアーカイブの中から現代の人々に合いそうな柄を選出し、そこから1年がかりで当時の技術に倣って復元を試みました。染料や、作り手が現代の人なので、まったく同じ物を作ることは難しいですが、日本が古来より紡いできた伝統や技術を絶やさないことが最も重要であると考えています」。


過去から学ぶ未来へのヒント
このように着物や反物の製造背景には、当時の人々の世相が色濃く反映されているわけだが、だからこそ泉二はそうした文化的背景の研究にも力を入れている。
「今まで続いてきた伝統に対して、何か新しい試みをする際に、僕は必ず過去にヒントがあるという価値観を大切にしてます。さまざまな資料を元に、歴史はもちろん当時の暮らしなどを細かく調べるようにしているんです。昭和の初期に今和次郎という方がいて、統計学を生業としていました。彼の著作の『考現学』という文献の中に、1925年の約100年前のデータが記されていて、ほんの100年前ですがまだこの時代の女性は99%が着物を着ていました。そう考えると女性が洋服を着用し出したのは実は本当に最近の出来事なんですよね。このように今の時代だけを見ているとわからない時代背景が沢山あって、どのように時代が移り変わってきたのかを知ることは、これからの時代を予測するヒントにもなり得るのだと考えているんです。伝統に対して向き合う時に、突拍子もないことをしてしまっては、その伝統を絶やしてしまうことにもなりかねません。日本の明治時代には、さまざまな外来文化が日本に入ってきました。そうすると、今まで当たり前であった草木染めのものが化学染料になったり、手織りのものが機械織りにとってかわりました。伝統というものは混沌とした時代も生き延びて今の時代に繋がってきています。起こった出来事に対して産地でどういう化学反応が起こったんだろうとか。その時代の人々がどういう価値観で出来事に立ち向かったのかとか。それを知ることではじめて、何を変化させてどこを守ってなどの思考のヒントが生まれます。守るべきものは守る、変えるところは変えるということが、伝統を革新していくためには必要なのです」。


人の繋がりが生む化学反応
伝統を受け継いでいくことも大切だが、伝統を作っていくこともまたこれから先の未来に対しては重要なこと。過去から学ぶという姿勢とともに、泉二が大切にしている要素がもうひとつある。それは人との繋がりの中で生まれる化学反応だ。「染織の可能性を探るプロジェクトとして、宮城県にある大蔵山スタジオという採石場と実験的な試みをおこなっています。イサムノグチがこの採石場から切り出した石を使って作品を作っていたことでも知られていますが、2000万年の歴史でマグマの噴き上げで2度海に沈んでいて、石の表面がどんどん海水と化学反応を起こして土に還っていく固有の現象が起きているんです。それを知った時、大地に還っていく石という概念は、日本の伝統的な染色方法の大地から染める草木染めと親和性が非常に高いなと感じました。昭和初期の文献に草木染め研究の第一人者である山崎斌(あきら)が書いた『日本固有草木染色譜』というものがあるのですが、その文献を作った作者の子孫が現在も草木染めの伝統を今に繋いでいるんです。このふたつの要素を掛け合わせて、何か新しい染色方法を模索できないかと考えたことがプロジェクトの始まりでした。採石場と草木染めの協業は普通ではあまりやらないことかもしれません。ですが万物は何でも染色原料になる可能性があるし、これがもしかしたら200年後には伝統になっている可能性も十分にある。織物染色の可能性を求めて新しい試みをすることで、そこに人が関わり予期せぬ化学反応が起きる可能性すらあると思うんです」。
実験を確信につなげ、やがてそれが伝統になるという考え方。泉二は呉服屋という枠を飛び越え、日本の伝統工芸を次世代に繋げていくべくさまざまな挑戦を続けているのだ。
「伝統工芸を伝承していく方達がこの先いなくなってしまうのではないかという不安があるなかで、自分たちの固定概念を捨てて未来に繋げる変化を起こすということを真剣に考えていかないといけない。本当は僕たちが携わる領域を超えてしまっているのかもしれないけれど、何もしなければ何も変わらないし文化が終わってしまうかもしれない。作り手がいてこその呉服屋ですから。人と人との関わりの中で、呉服を中心とした日本文化や伝統に新たな道筋を作っていかなくてはならないのです」。


泉二 啓太
1984年生まれ。呉服屋銀座もとじ二代目。学生時代はロンドン芸術大学にてファションを学ぶ。呉服文化を次世代に継承するべく、日々挑戦を続けている。
◯ 銀座もとじ
https://www.motoji.co.jp/
| Photo Tomoaki Shimoyama | Interview & Text Shohei Kawamura |