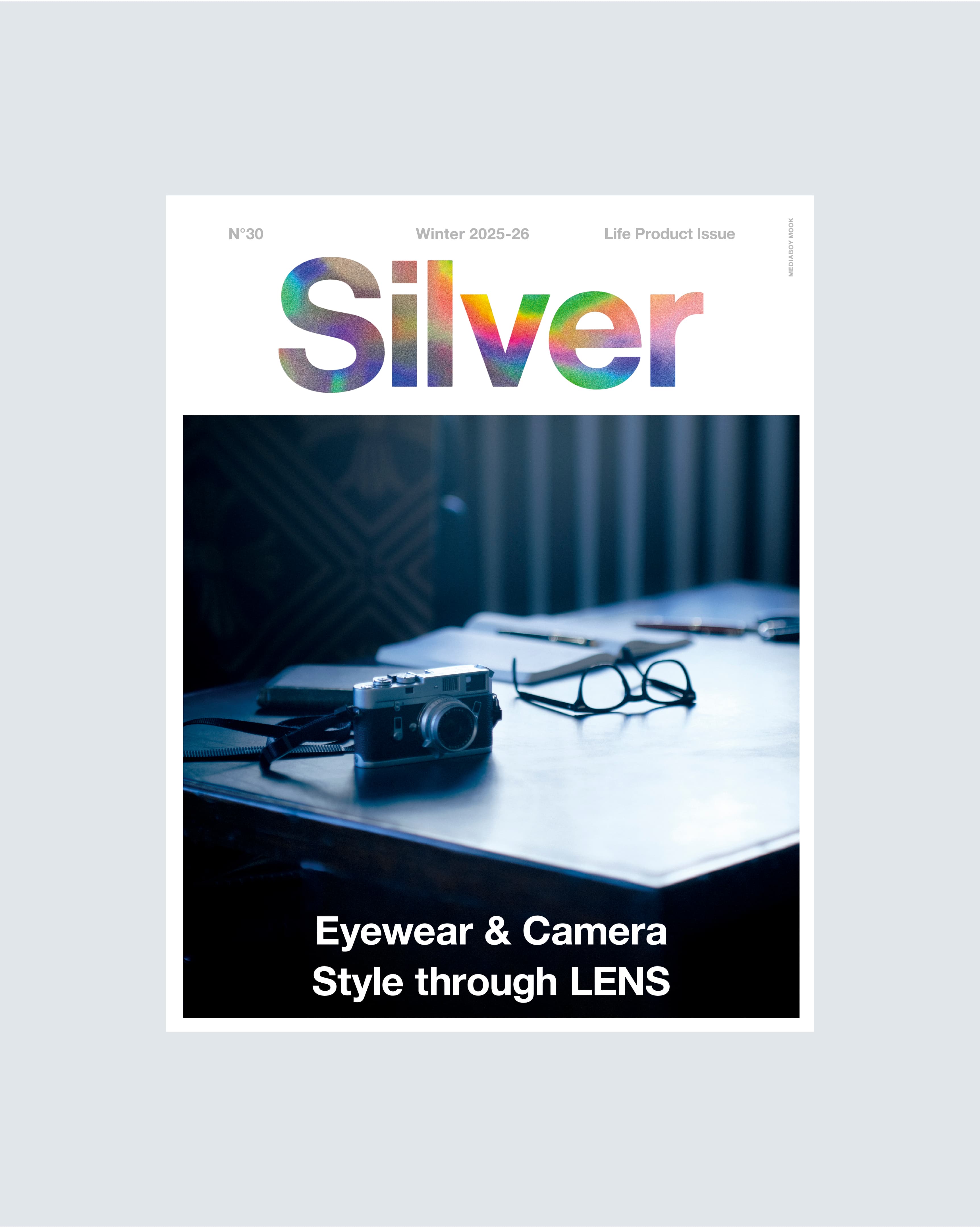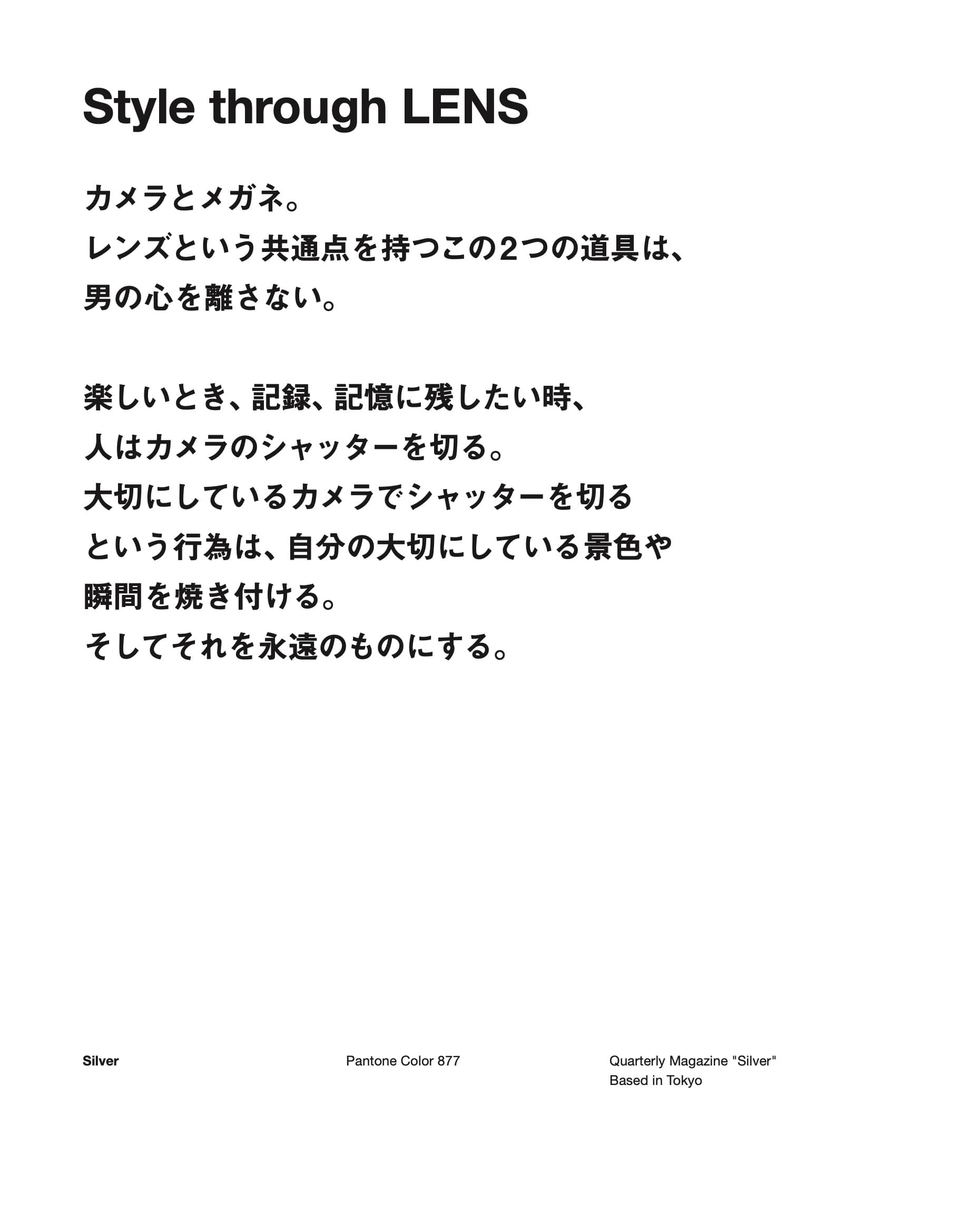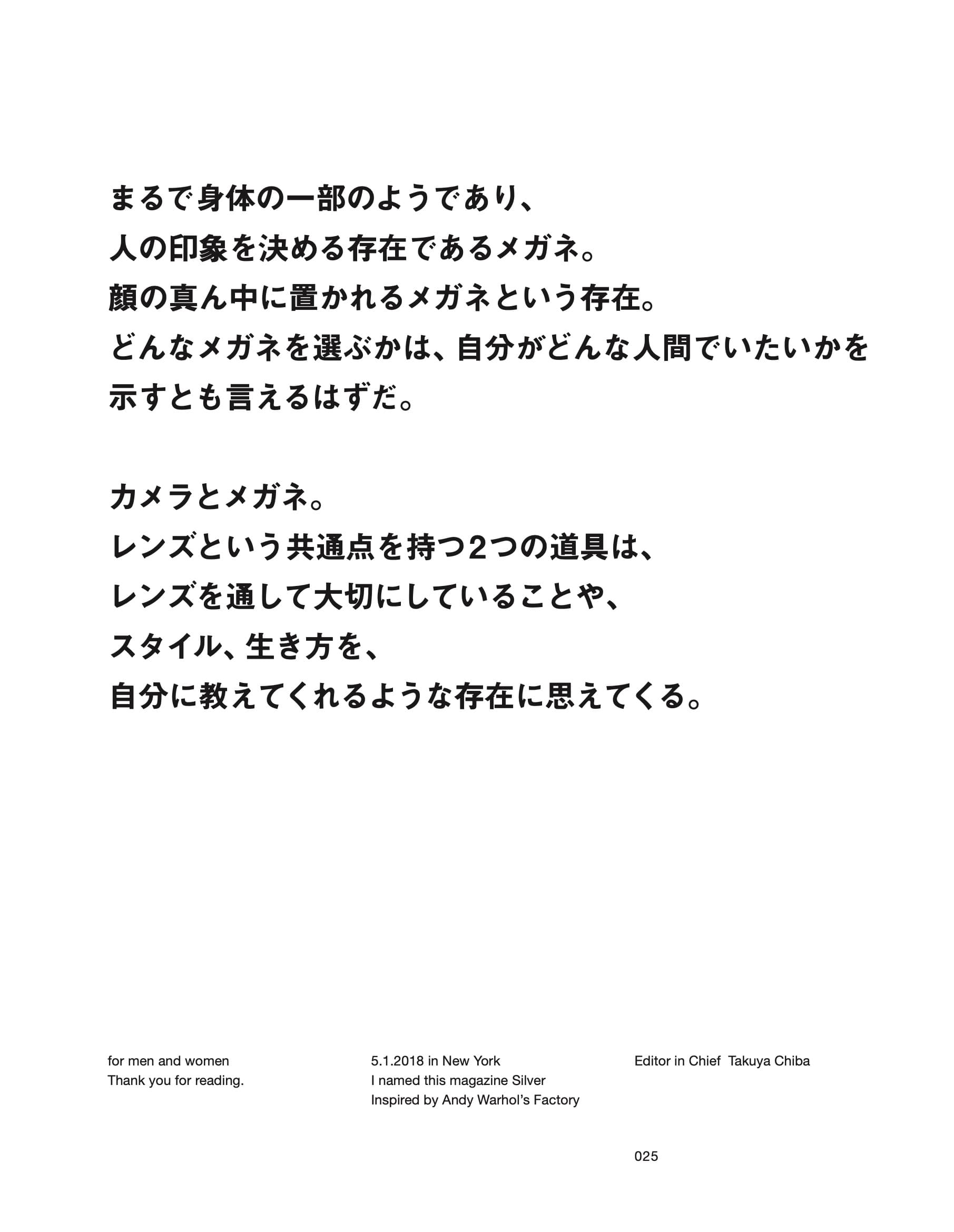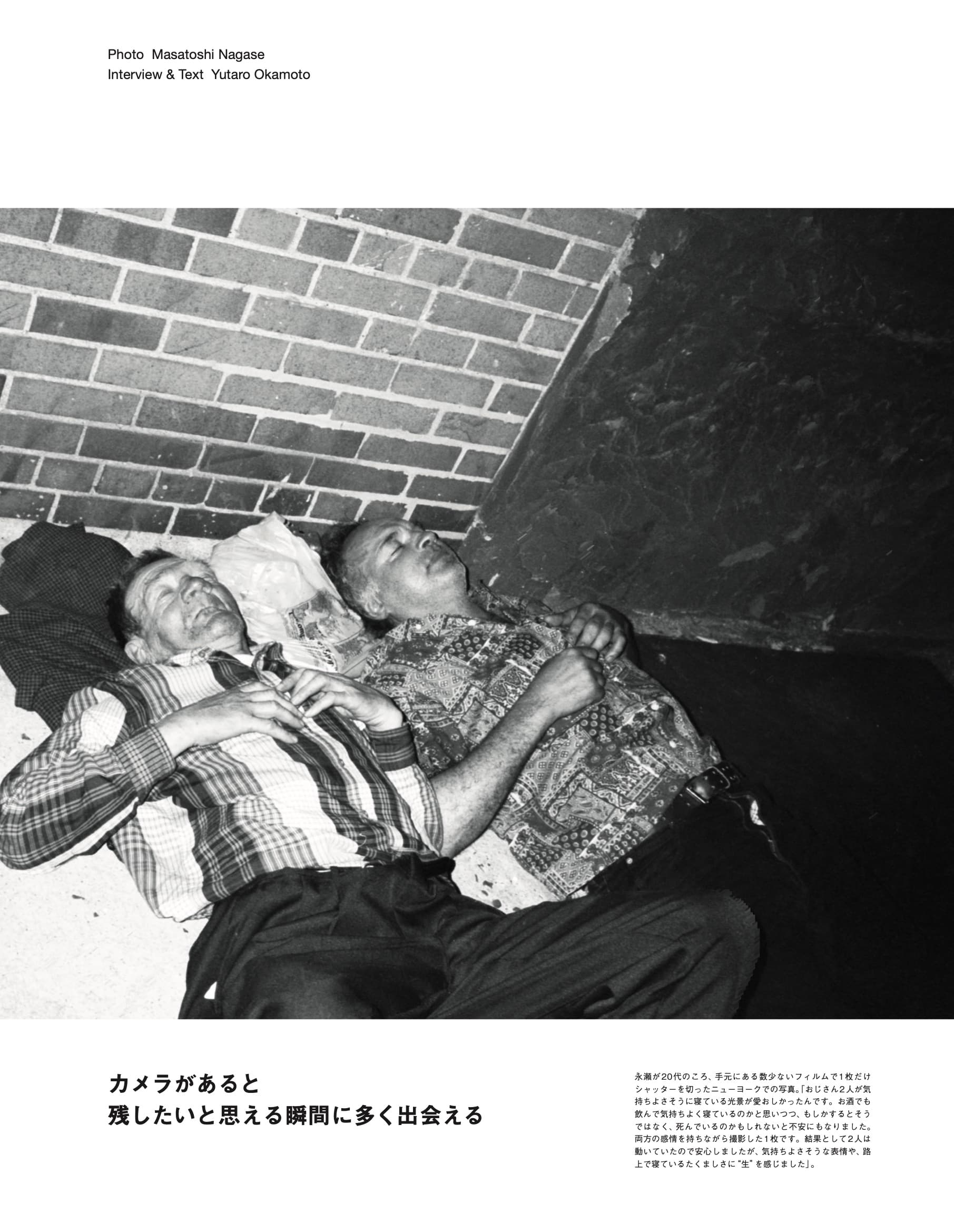Interview with Ryo Kashiwazaki (Hender Scheme)
ものづくりの長い歴史 その延長線上で生まれる知恵

¥41800 by Hender Scheme (sukima Ebisu)
文化や産業っていうのは
繋がって成熟していくもの
動物の皮を用いて足を守るというアイデアに、ヒトは紀元前にはもうたどり着いていたという。そして15世紀ごろには、現代に近い革靴の原型がすでにあった。そんな歴史に触れると、靴づくりというのが脈々と受け継がれてきた文化であることがよくわかる。製靴業からものづくりの世界へと足を踏み入れた柏崎亮は、そうした文化の重みを実感しながらも、“ヘリテージ”という表現については「僕にとっては実は少し縁遠い言葉」と、バツが悪そうに笑ってつぶやく。
「僕らより上の世代の人たちには、それをベースにものをつくってきた方々が多いと思います。もちろんその方法論に対して理解も尊敬も持っています。でも僕たちは、少し大袈裟かもしれないけれど、特定の時代やカルチャーをリファレンスとしてアプローチする方法だけではない、新しい方法論そのものを構築したいんです」。伝統がある分だけ、絶対的な正義がえてして生まれやすいのがシューメイキングの世界だ。ヒエラルキーの頂点にはビスポークがあり、当然歴史が深く、技術や品質が高いところの発言力が強まってくる。「だから、僕のこういう考え方はあんまり受け入れられないんですけどね。ずっとひとりでカベ打ちをしてるような感じです(笑)」。
ものづくりに従事した時間が長く、確かな矜恃を持つ人ほど、古くからの価値観や慣習に染まりやすいのは無理もない。しかし、柏崎のものづくりはいつだってそうした当たり前をまず疑うことから始まる。
「なるべく既成の概念を査読するというか。僕らは“フリップする”って言うんですけど、権威的なものに対してどうやって違うアプローチをしていくかを考えています。『この角度があったんだ』って、ひっくり返すような」。
「例えば…」と言って柏崎は1足の靴に手を伸ばす。プレーントウでヒールにはレザーのストラップがあしらわれたデザインだが、そのストラップが3本、色違いで付属していて付け替えられるというものだ。「バックストラップの端の部分が両方バックルになっていて。ベースはドレスシューズなんですけど、そこに新しいアイデアを上書きしてるような感じです。だからベースとなる部分はしっかりつくります。そこはクオリティを担保しないと成立しないから」。エンダースキーマのショールームには、そうした柏崎の視点から生まれたシューズが無数に並ぶ。「やっぱり革靴ってあまり更新されにくい文化なので、まだ余白がすごくあると思う」と彼は言う。
兼ねてからエンダースキーマは“ニュークラフト”という言葉を掲げてものづくりを続けてきたが、靴作りでえたレザー使いのノウハウが生かされた小物類にも、そんな姿勢が滲んでいる。今季初めて登場した“シームレスウォレット”はその名の通り縫い目が表に現れないのが特徴で、まるで裁断した革をただ二つ折りにしたかのような、とことんミニマルなデザイン。もちろん中には札入れやカードスロットが備わっているが、そこに必要なステッチが外からは見えないという違和感がポイントだ。実はこれは革を薄くするための漉き割りという技術を応用したもので、通常は完全に剥がし切る銀面(表)と床面(裏)を一部だけ繋がったままにすることで成り立つアプローチだ。「漉きが入っていないところは繊維がそのまま繋がった一枚革の状態で、床側にだけステッチをかけたらまた貼り付けて、最後にコバを磨いています。革を折ってもアタリが出ないようにするのが難しくて、サンプルを5回程つくり直してようやくうまくいきました」。

¥37400 by Hender Scheme (sukima Ebisu)
文知識の有無よりも
知恵が大事
先のシューズが可変トラップという発想が発端なら、このウォレットは言うまでもなくレザーの加工技術先行で生まれたもの。プロダクトの生まれるきっかけやヒントは、色々なところに散らばっている。
「ケースバイケースで、デザインから入る時もあれば素材から入る時もあるし、こういう技術から入ることもあります。技術から入る方が、かけた時間とプロダクトの良さが比例していくので健康的につくれますね(笑)。アイデアはただ実行すればいいってものでもないから、もっと不安定です」。ところで、この技術の面白さに柏崎が気づいたのはエンダースキーマを立ち上げるよりも前、まだ彼が工房で靴の修理に携わっていた時だったという。「当時、僕の先輩が持ってきた靴でキャロルクリスチャンポエルのブーツがあったんです。裏地なしの1枚革なのにファスナーのテープの端が露出していなくて、それがすごいなという記憶がずっとあったんです」。
柏崎は自身のリファレンスや着想源について普段はあまり語らないし、実際に特定の元ネタが無いところから生まれるアイデアも多い。けれど、彼がふと話してくれた昔話からは、彼が先人たちのものづくりから少なからず影響を受け、そこに対して敬意を払っていることが確かに伝わってくる。
「自分自身でものづくりをしていても、数シーズン前の知見がこれに活きた、みたいなことの連続です。ましてや靴をつくっているっていうことは過去から今が地続きに連続しているということ。俯瞰して見れば、文化や産業っていうのはそんな風に繋がっていて。そうやって成熟していくものだと思っています」。
エンダースキーマを始める前から今になっても、世の中のいわゆるオーセンティックな革靴への礼讃は変わらず根強い。
「でも、これは日本特有のものだと感じています」と彼は話す。パリでの展示会を重ねていく中で、その確信は強まっていったようだ。「僕らのバランス感覚って、パリではすごく受け入れられやすくて。老舗で良い靴っていうのは向こうではもっと日常的なもので、そこにはクラシックに飽きている人や、スニーカー以外で何か新しいものが出てこないのかと期待をしている人がたくさんいるんだなと実感しています」。
日本人の探究心は世界に誇れるものだし、実績だって枚挙にいとまが無い。ただ、時として権威への尊敬が盲信へと変わってしまうというのは皮肉な話だ。柏崎は物事を掘り下げはしても、知識というものに対してはニュートラルな姿勢を崩さない。
「是でもないし、非でもないという感じです。今は知ろうと思えば5分でものが知れちゃう時代だし、知らない方が良いこともたくさんあると思います。僕らにとっては知識の有無よりも、その知識をどう活かすかという知恵の部分がすごく大事なんです。知識を基にどう表現するのか、どう構えて、どう営むのかっていうところに興味があります」。
そうしてものづくりと向き合ってきた結果、エンダースキーマは多くのフォロワーを生んだ。それを踏まえて、「エンダースキーマに似たものづくりをするブランドやつくり手に対して、どう思うか?」と彼に問いかけた。この意地の悪い質問に対して、柏崎は「歓迎されるべきことだと思います」と間を置かずに答える。
「あまりにも商業的で悪意のあるものはある程度制限すべきだと思うけど、例えば僕らがよく使っているヌメ革やナチュラルレザーみたいなものって元々ある素材だし、それで近しいアプローチをしていてもまったくもって構わないという感じです。僕らは“二次創作”という言葉をよく用いますけど、それが単純に二次だとは思っていなくて。三次、四次、五次ってずっと連続しているものづくりの延長線上に僕らがいるだけ」。世の中が一次だとしているものにすら、きっと我々が知り得ない、別の一次があったりするのかも知れない。柏崎の見方はそんな気付きを与えてくれる。「それはつまり、点が繋がって線になっているということ。だから、僕がやったことに対しての二次的、三次的なものについても、それが意図されていようが無意識だろうがネガティブな感情はまったく無いです」。
自分自身がものづくりの歴史という大きな流れの中の一部であるという実感が、柏崎にはある。ただ自分の権利だけを追い求めていては、きっとそうした視点にはたどり着かなかっただろう。
「そこはもうちょっと冷静に考えてもらえると良いなと思います。権利を主張して制限をかけるということは、同時に自分自身も自由を一部失うということ。そこはトレードオフなんです」。権利で保護されれば、そこに他者の視点や新しいアイデアが入り込む余地は当然なくなる。それはそのまま、ものづくりの発展の停止を意味している。「だから立体商標っていうのは取りにくい訳で、権利的な部分はこれからものづくりをしていく人たちも直面する問題でしょうけど、何でもかんでも権利を主張し出したら、何も生まれなくなってしまいますよね。ヴィンテージやヘリテージだってつくり手がいたものだし、自分で考えつくことを自然に他の人が考えつくことだってあり得るっていうくらいの気持ちでいた方がいいと思います。そういう意味ではコール&レスポンスでものをつくっていけたら楽しいんだろうなと思う時もあるんですけど、相変わらず自分で打って、また打ち返してみたいなカベ打ちの繰り返しです(笑)」。

¥53900 by Hender Scheme (sukima Ebisu)

¥59400 by Hender Scheme (sukima Ebisu)

¥59400 by Hender Scheme (sukima Ebisu)

¥53900 by Hender Scheme (sukima Ebisu)
お互い消費し合うより、
もっと先に種を撒く感覚
そうした自問自答の一端が、“mip”に現れていることは明らかだ。既視感のあるフォルムをヌメ革と革靴の製法で表現したこのシリーズは、アイデアとは、デザインとは誰のものなのかと、我々に静かに問いかけてくる。
「僕はあのタイミングでmipを制作したことで二次創作的な表現の幅を広げることに成功したのではないかという自負がありますが、あまり批評的に語ってもらえていません(笑)。どうやって線を引いても中間のグレーゾーンは残って、そのグレーゾーンで何か定義できないことをやるっていうのが僕は好きだし、やりたいことのひとつでもあります」。
アンバランスな中間地点。白でも黒でもない場所。エンダースキーマが営む“スキマ”というショップの名やキーカラーのグレーも、やはりそんな立ち位置を物語っている。先頃始まった大阪の新店は、古民家だった元の建築を活かしながら改装ではなく“加装”していくという考え方でつくられた。これも、ある種の二次創作だ。余談だが、この店名は過去に行ったイベントの名前に由来するそうで、柏崎は表記を漢字にするかカタカナにするかで悩んだと言う。結果採用したのは後者だったが、前者のアイデアも晴れて今年、日の目を見ることになった。定期的にアーティストを招致し、展示を行うオルタナティブスペース。それが通称“漢字隙間”の全貌だ。
「元々エンダースキーマの営みの中で、もっと非営利でお金じゃない豊かな何かを生み出せるようなことをやりたいなと思っていて。それで、一度お金に交換することをせず、価値と価値をダイレクトに交換するということをやってみたいなと。それで、物々交換で展示をやれるスペースを始めようと思ったんです。アーティストはそこで作品を見せたり販売したりするんですけど、販売した時のコミッションを僕らは一切もらわない。だから、売り上げは全部アーティスト側に行く。その機会の代わりに、そこで展示した作品のひとつと、展示空間を通して目に見えない刺激を受け取るっていう」。クリエイションにも金銭にも直結しない、長期的な視点でのコラボレーションがやりたかったと柏崎は話す。「お互い消費し合うようなリレーションというよりは、もっとその先に種を撒くような感覚です。すぐに収穫するような即効性のある何かとは距離を置いて、わかりやすい実を得ないっていうことがどういうことなのかを体験・体感することで、自分たちがやってる経済的な営みについても俯瞰して理解できるんじゃないかな、って」。
“当たり前”への疑問提起は今ではものづくりを取り巻くすべての物事にまで及び、査読は絶えず繰り返される。それでも、柏崎が声高にそれを叫ぶことはない。
「(立川)談志が『意味じゃなく、音で笑わせろ』と言ってましたけど、僕らもやっぱり音でやってるんです。もちろん意味はあるけど、目的と手段をぐちゃぐちゃにはしたくないから」。
時折、下町の風情を覗かせるこの蔵前の町で、柏崎はきっと明日も寡黙にカベ打ちに励むのだろう。靴づくりの、ものづくりの系譜に、新たな点を添えるために。



| Photo Masashi Ura | Text & Edit Rui Konno |