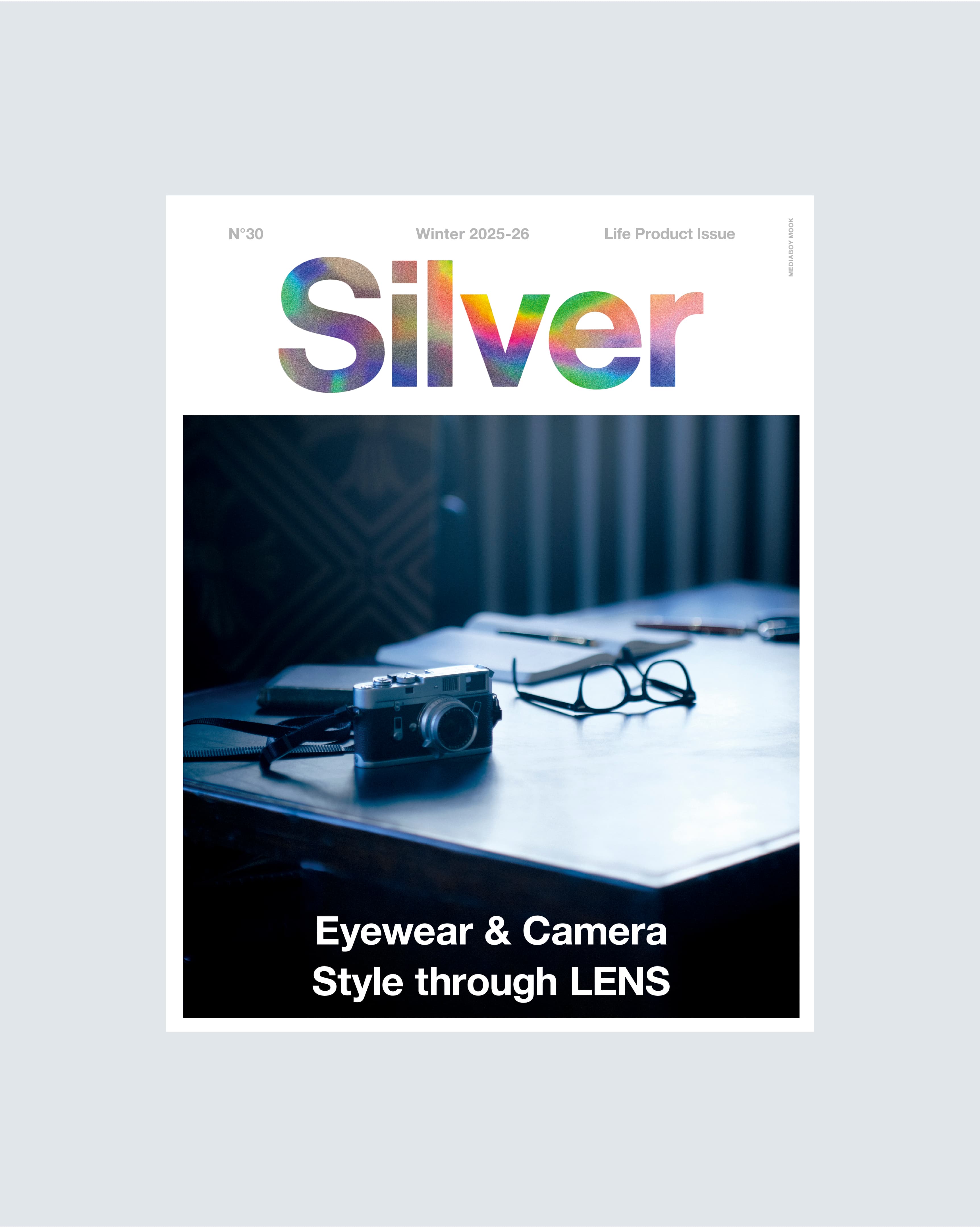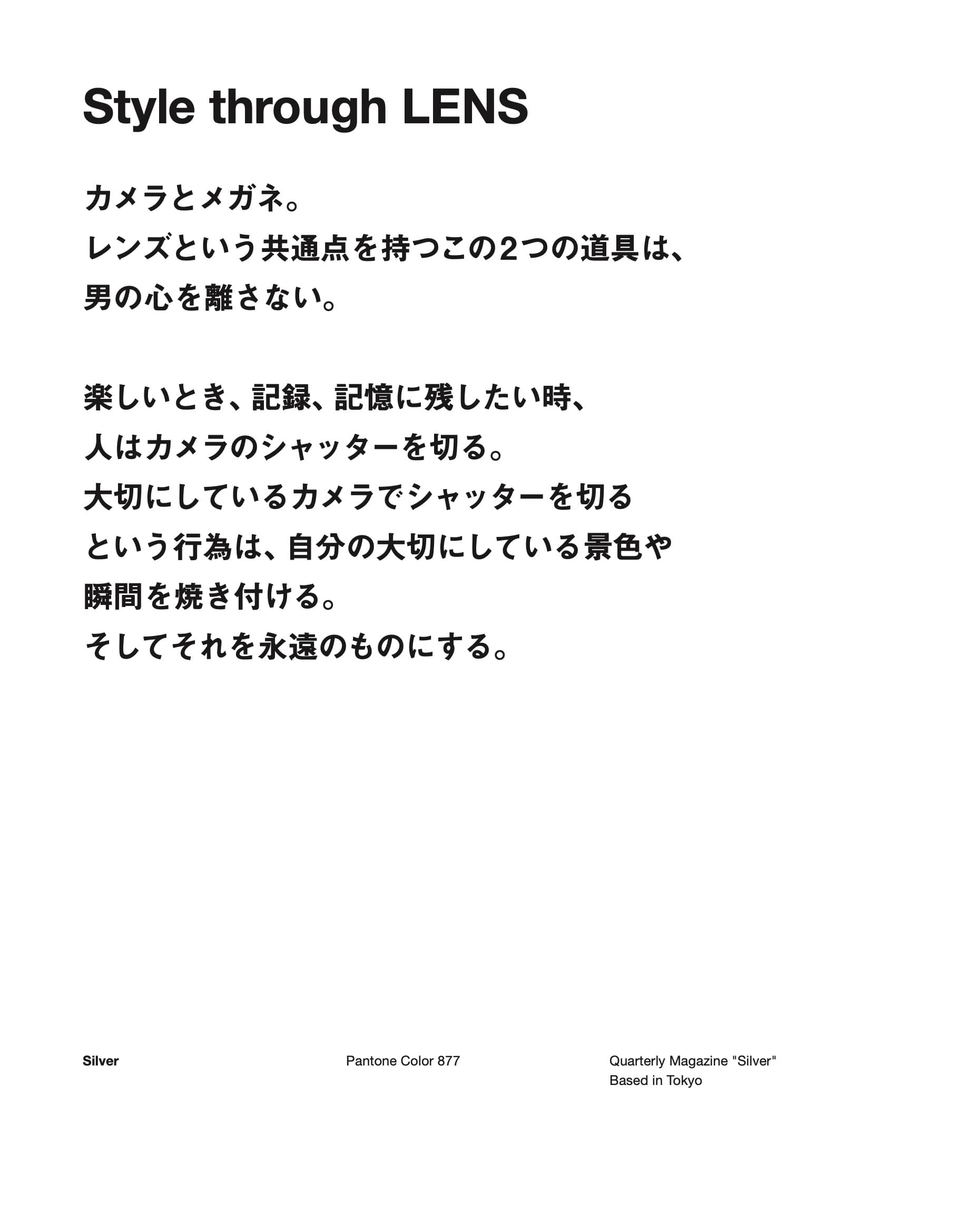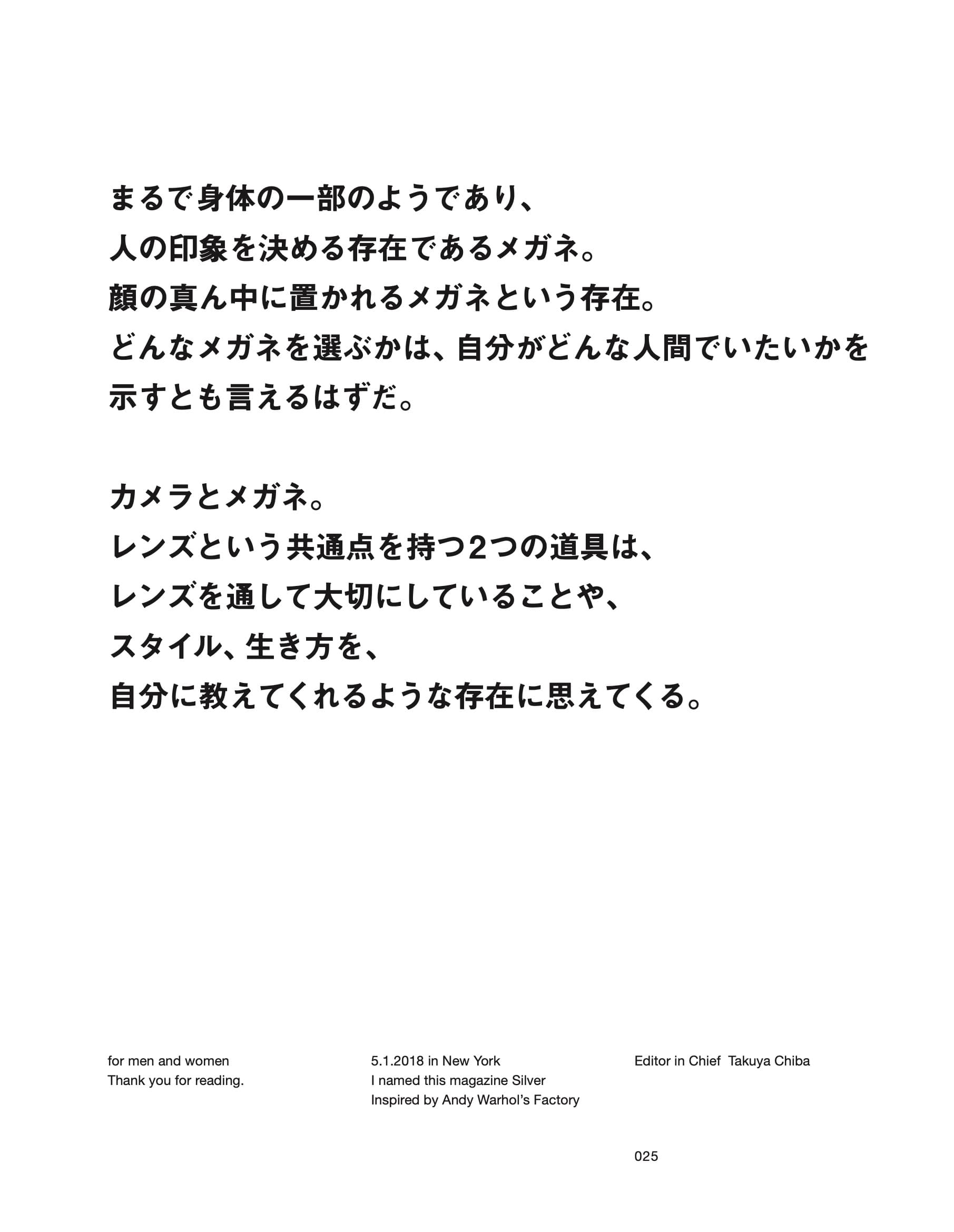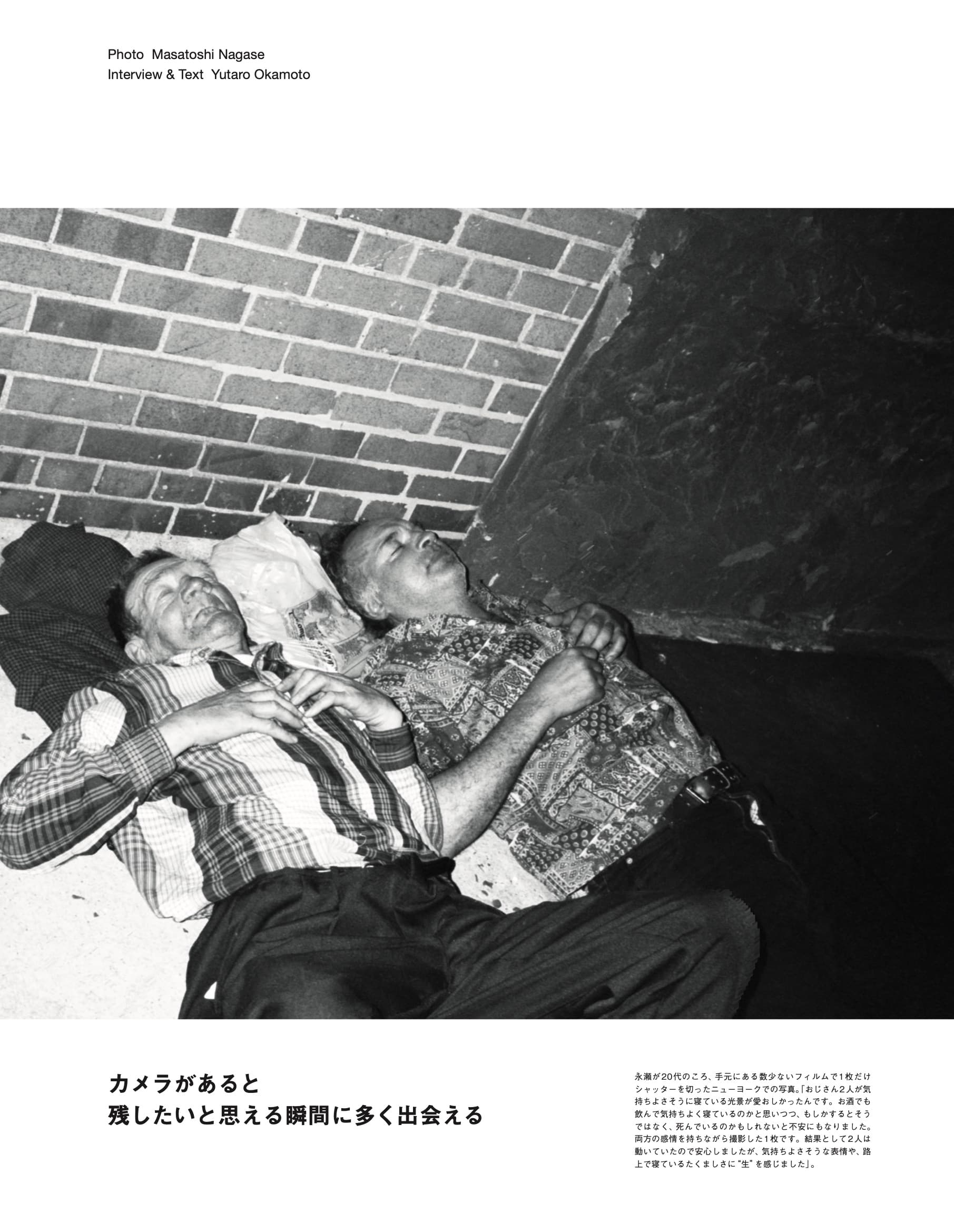Style File 06 Designer Takayuki Fujii
藤井隆行が考える 品性を磨くことの大切さ

品性を磨く様々なことは
洋服以外の文化が教えてくれる 藤井隆行
日本を代表するブランド、ノンネイティブのデザイナーとして20年以上活躍し続ける藤井隆行。シンプルで、上品で、どこか繊細で。長く愛される洋服を生み出し続ける彼のスタイルの源とは何か。その答えを探しに藤井の自宅である葉山に向かった。
家具も洋服も基本形は
60年代に完成されている
現在も毎日、車で中目黒のオフィスまで通勤しているという藤井。そもそも彼はなぜ葉山を住処に選んだのだろうか。そんな問いからインタビューはスタートした。
「葉山に住みはじめたのは2017年。デザインをする上で洋服だけでなく、家具にも目を向けはじめていた時でした。デザインの歴史を遡ってみると、家具と洋服ってとても似ているので、見ておかなくてはいけないと思ったんです。どちらも基本形は60年代に完成されているんですよね。それ以前の時代はデコラティブなものがたくさんあったと思いますが、60年代になってモダンなデザインが多く生まれた。そうやって調べていく中で、欲しい家具がどんどん出てきたのですが、当時住んでいた東京の家には置くことができない。東京の生活に息苦しさも覚えはじめていた時に、見つけたのがこの家でした。広くなったので、欲しかった家具も手に入れられるようになったし、生活も一変しましたね」。
日本青年館の設計に関わった建築家の手によって作られたというこの住宅。玄関を上がると、リビング、ダイニング、和室が仕切りなく設計された解放感ある間取りが広がる。大きな窓から入る陽射しもとても心地よい。そんな中に並ぶシャルロット・ペリアン、ピエール・ジャンヌレ、ジョージ・ ナカシマら錚々たるデザイナーの名作と呼ばれる家具たち。日本とフランスが自然と調和した趣ある空間に仕上がっている。
「家具について調べていく中で、日本とフランスがつながっていることを知ったんです。例えばペリアンを紐解いていくだけでも、柳宗理、河井寛次郎、ジョージ・ナカシマなどの名前が出てきます。日本とフランスの関係性がすごく見えてきた。それらに関係ある家具に惹かれ、購入しています。 レアなものだけを購入しているわけではないんです。家具もスタイリングだと思うので、買うにも理由がないと嫌なんですよね。例えば和室に置いてあるペリアンのキャビネット。寸法を調べただけで購入したものですが、置いてみたら驚くほどぴったりハマった。これは柳宗理らと交流を深め、日本を勉強したペリアンだからこその日本の住宅に馴染むデザインなんだ、と思いました。ダイニングで使っているジョージ・ナカシマのテーブルも一般的なものより5センチぐらい低く作られているんですが、それはペリアンが日本で床で生活するスタイルを知って生み出した、天井を高く見せるための手法なんです。このように日本とフランスってお互いに影響を与えていることが多い。建築もそうですよね。コルビュジエがいて、坂倉準三がいて、吉村順三がいて。その繋がりの中にイサムノグチもいて。コルビュジエからなる建築の文脈を辿ると、多くの日本人建築家の名前が登場する。共通するのは、文化に対する価値感だと思うんです。料理だって、出汁の文化を一番理解しているのはフランス人じゃないかな。だからパリコレにもあんなに多くの日本のブランドが出展しているんだろうし。世界中に色々な国があるけれど、勉強を重ねてみて、僕は上品さとストーリーを持ったフランスのデザインが好きなんだな、と思っています。どんな家具でもなぜその形になったのか、その理由がはっきりしているストーリーがあるデザインが好きなんです」。

自宅の随所にレイアウトされている藤井が選んだ名作家具の数々。写真左上はシャルロット・ペリアンとピエール・ジャンヌレ共作のキャビネット、右上はジョージ・ナカシマのグラスシートチェア、左下はジャンヌレのオフィスチェア、右下はアトリエ2+のスツール。高いデザイン性は、そのいずれもが空間に馴染む。

この家を選ぶ上でポイントだったという和室は、名作と呼ばれる家具と伝統的な畳・障子が絶妙にマッチしている。藤井のスタイルを紐解く上でのキーワードである“日本”と“フランス”の融合を象徴する場所だ。

大きな窓からは自然光が差し込み、庭の植物が安らぎと癒しを与えてくれる。季節の移ろいも感じられる葉山ならではのゆったりとした時間が流れるこの環境から、藤井のクリエイティブは生み出されている。


落ち着きたい時に、1人で裏の山を走る。精神安定の効果があるというトレイルランニング。「目に入る植物の色味は、デザインにも自然に反映されているはず」と語る藤井。東京では決して味わえないアクションだ。
メンズの洋服はユニフォーム
デザインの背景、ストーリーがある家具に惹かれるという藤井。そのマインドは洋服作りにも生かされている。
「僕はメンズの洋服はユニフォームだと思っています。ユニフォームと呼ぶからには、機能性をキープしなくてはいけないですよね。また、ストリート感も絶対に必要なものだと考えているんです。僕の言うストリート感ある服というのは、カルチャーとしてのストリートという意味ではなく、道を歩く人、つまり生活する人のための服であるべきだということ。例えば6ポケットのミリタリーパンツ。サイドポケットは何の必要があるのか、そういった疑問を日々持ちながらデザインしているんです。シルエットを変えるために必要だという捉え方もあるけど、そもそも取り付けられた理由を理解せずにポケットをつけるとミリタリーパンツではなくなってしまう。そうやってベースとなるものをキープしながら、新しくすることは常に考えています。そのアイディアを得るためには、洋服と向き合っているだけでは難しい。だからこそ、家具や車にも目を向け、常にデザインと機能について勉強しているんです。でも一方で、そのストーリーを説明したくないとも思っているんです。それは、洋服はあくまで“着たらかっこいいじゃん”という見た目がまずベースにないといけないと思うから。だからお店のスタッフにもあまり服の背景を説明はしていません。機能やストーリーで価値を語る前に、まず見た人が感じてほしい。そのように考えているので、デザインもひと目でブランドがわかるようなものにならないよう意識しています。ファッションの第一印象が攻撃的になってしまうのが嫌なので、メッセージ性の強いものも作っていません」。また、20年以上にわたってデザイナーとして活躍しながらも、1つのアイテムに固執しない柔軟な発想とアティテュードも彼の魅力だ。
「ここ数年は太いものが主流となったジーパンに悩まされてます。これまで、僕は日本人の体に合うように緻密に計算してパンツを作ってきましたから。でも、これだけ太いものが出てくると、やっぱり太いものも作ってみたいという欲求が出てくるんです。そういった姿勢はすごく大事にしています。1つのものに固執して、物事を深掘りしすぎると、頑固でオーセンティックなものばかり作るようになり、フラットな視点がなくなってしまいますから。洋服を作る上で知っておかなくてはいけないことはたくさんあるけど、その知識をあまりアイテムに落とし込みすぎないことが大事だと思うんです。やっぱりずっとジーパンを作っているブランドには勝てないし、そもそも勝とうとする考え方自体が違うと思うので。ノンネイティブは上品さをすごく大切にしているブランドです。僕が作った服は上品な人に着てほしい。では上品さ、品性とは何か、ということを考えると、着る人も作り手も一生をかけて磨いていかないといけないものだと思うんです。その品性を磨く様々なことを、家具や車など洋服以外の文化が教えてくれます。だからこそ僕は家具に惹かれるんでしょうね」。
民芸的な“アート”ではなく
工業製品的な“プロダクト”
フランスの民芸的、調度品的な家具を愛する一方で、自身が生み出す洋服は工業製品的な“プロダクト”であると言い切る藤井。「僕の作る洋服は、民芸的な“アート”ではなくプロダクト。1個1個違ってはいけない。100枚だろうが1000枚だろうが同じものを作らないといけないと思っているんです。そういう意味では、工業製品に近いですね」。そんな藤井は、この秋アンダーカバーとコラボレーションしたプロジェクト“オジズム”の第2弾を展開する。アンダーカバーとノンネイティブ。異なる哲学を持った両者のタッグだが、その制作の背景にも日本とフランスというキーワードがあった。「ジョニオ(アンダーカバーデザイナー:高橋盾氏)さんは、僕とものの見方や考えていることが全然違うから話すのが面白いんです。例えば絵を描くという表現1つにしても、ジョニオさんは苦もなくやるけど、僕はそれができない。逆に工業的に服を作るということについては僕の方が得意としている。最初のコレクションでは“和”をテーマに作務衣を作りました。服作りとしては新しかったですね。例えばタグネームを表につけたりするデザインは、僕はあまりやらないけど、ジョニオさんは昔から得意ですから。新たな発見もありつつ、僕の意見も出しながら完成しました。そもそもオジズムっていうのは小津安二郎にインスパイアされたもの。2人とも小津安二郎の淡々とした世界観が好きなので。次のコレクション(2024年春夏)では全部和紙と綿を混紡した素材に草木染めした服を作っているんです。そしてそれをパリでお披露目する。フランスと日本という話がここでも繋がるんです。昔はフランスに行くのはあまり好きじゃなかったけど、このコレクションのために年2回は行くようになった。新しい感覚です。今ではアメリカよりも魅力を感じています」。
目指しているのは
海外旅行で選抜される服
ノンネイティブのイメージといえば、ベージュやグレー、ブラウンなどの中間色。この日の藤井の装いも、前述したアンダーカバーとの共作コレクション“オジズム”のブラウンの作業着だった。
「僕はスタイリングを考える時、靴から決めていくんですが、洋服が中間色であればどんなシューズを合わせてもまとまる。背が低いから同じトーンでまとめると小さく見えないという理由もありますが。そもそも“ノンネイティブ”っていうブランド名自体が、ニュートラルという意味ですから。どこにも所属していない、ふわふわしている。逆に言うと何でもないブランドになってしまう。それはとても危険なことなので、ノンネイティブというジャンルをどうやって作るか、というところは、すごく気にしてやってきました。そのブランディングの一つが色なんです。スケート、バイクなどのカルチャーではなく、色。先程お話ししたことと重なりますが、僕は背景に精神性を持った洋服は作っていません。あくまでプロダクトとして成り立つようにしているんです。例えばナイロン素材のウエアを作るときは、リサイクルナイロンを必ず使うようにしていますが、それを打ち出すことはしていません。SDGsなどと語るよりも、着ている人の第1印象が服で判断されないような服を作っているつもりです。存在感は強くないけど、でも何かいいものを着てるね、みたいな印象になればいいと思っているんです。言うなれば“海外旅行に行くとき、ワードローブの中から選抜される服”を目指しているんです。雨が降るかもしれないし、風が吹くかもしれない。いろんな場面に対応して、ちょっといい印象が与えられる安心感のある服。僕が作った服から、手に取った人がそんなことを感じてもらえたら嬉しいです」。
名作絵画や家具は飾らない
藤井は8月にノンネイティブ初となるフラッグシップストアを中目黒にオープンさせた。温かみのある木の床、白い壁、独特の形の間口。どこかで見たことがある。そう、藤井の葉山の自宅にとてもよく似ているのだ。「あまり意図していなかったんですが、壁と什器を最初に決めて、なるべくフラットになるように作っていったら、いつの間にか“あれ、我が家とめっちゃ似てるな”と気づいた(笑)。でも家と違うのは、名作と呼ばれる絵や家具を飾らない、ということ。きっと洋服よりも目立ってしまうし、そういうものが好きな人を対象にしていると思われてしまうから。だったら何もない方がいいと考え、できるだけニュートラルな空間を目指しました。その代わりに僕が自分で大きな椅子を作りました。自分の中ではシャルロット・ナカシマと呼んでいます。ジョージ・ナカシマの脚とペリアンの天板。わかる人にはわかるアイテムです(笑)」。
洋服だけでなく、家具をはじめとしたデザインについて深く突き詰めて考え、ストーリーを紡ぎ、生み出されるノンネイティブのウエア。デザイナー藤井隆行が生み出すプロダクトには、確かな奥行きがある。デザインの歴史、ストーリーを踏まえつつも、それを全面には主張しない。その奥ゆかしさが品となり、情緒となる。それこそが藤井のスタイルであり、だからこそ彼が生み出す洋服は多くの人に愛され続けているのだろう。これまでも、これからも。

藤井にとって人生で究極のシューズであるというGUIDIのセンタージップブーツ。nonnativeでも幾度もコラボレーションを行なっている。長時間歩いても疲れず、合わせるスタイリングを選ばないため、海外旅行に行く際には3足持っていくとのこと。


8月にオープンしたノンネイティブ初の旗艦店。写真左で中央に鎮座するのが、家具の知識を活かして藤井が作った椅子。写真右に見える2つのスペースを繋ぐ間口は、藤井の自宅のキッチンの入り口と同じデザインとなっている。
東京都目黒区青葉台1-16-17 2F
03-5990-4720

藤井の好みが反映されているというノーカラーのジャケット。ミリタリーパンツは、機能性とデザイン性を共存させるべく、ポケットの位置まで緻密に計算され、モダンなムードにアップデートされている。

| Photo Kei Sakakura | Edit Satoru Komura |