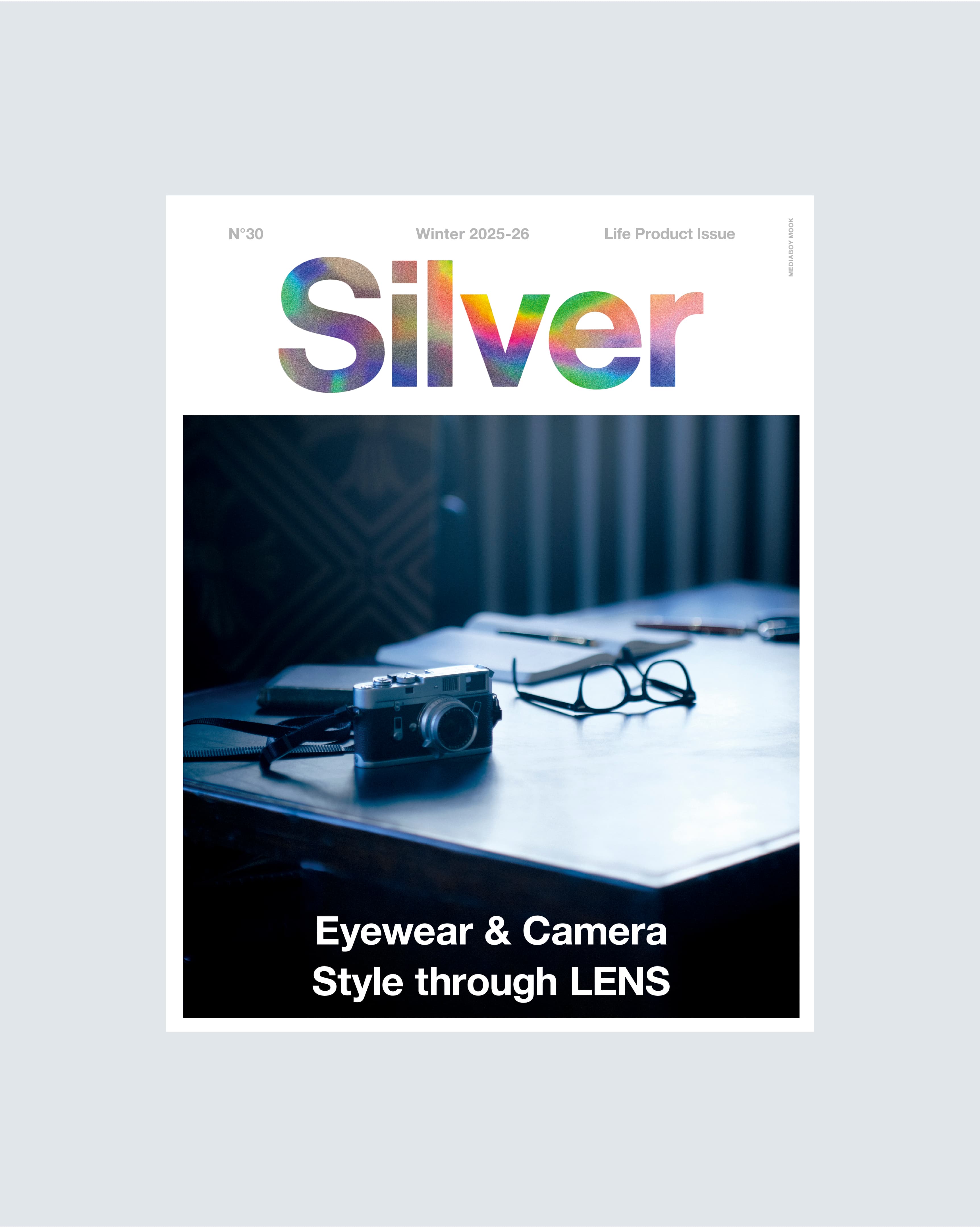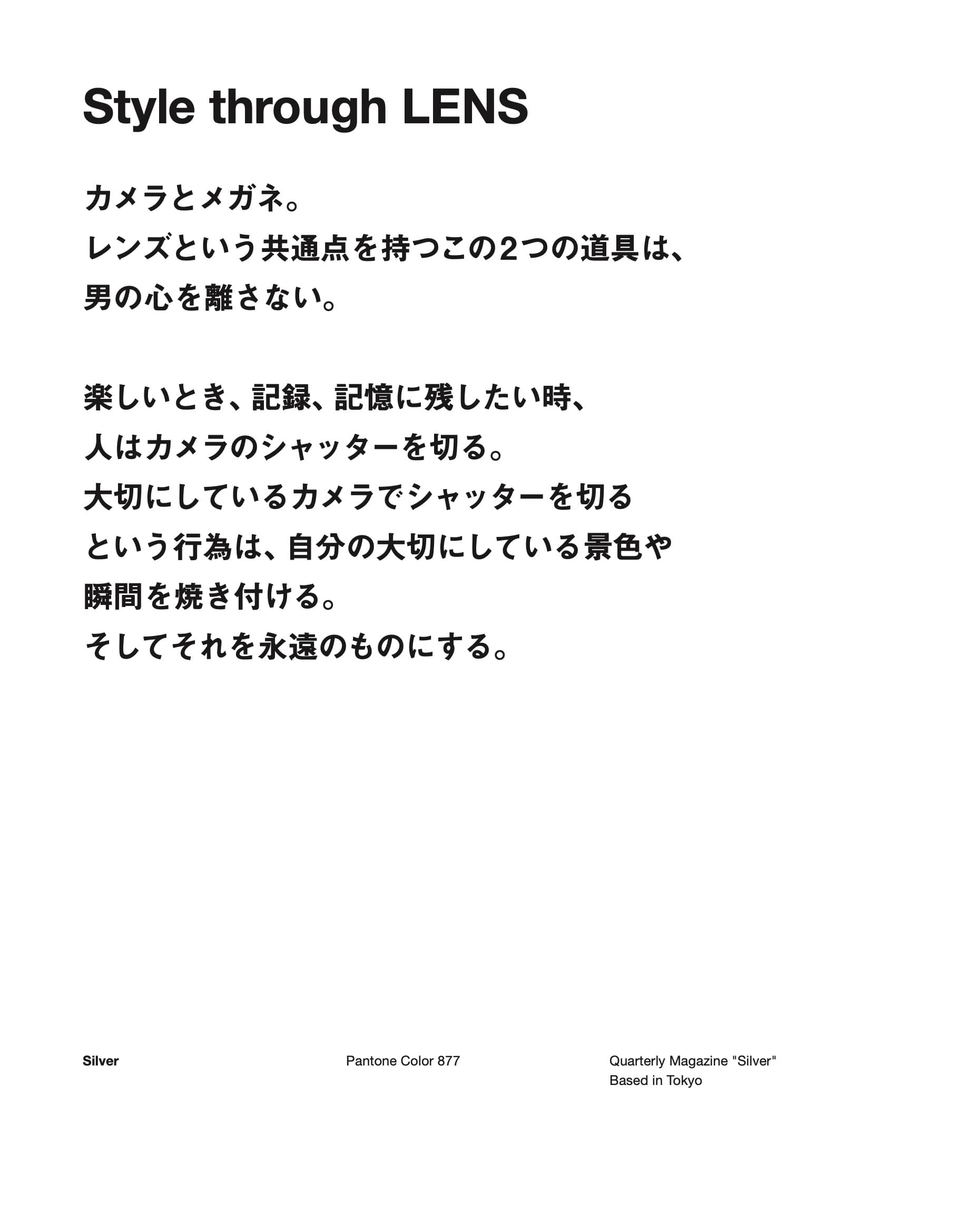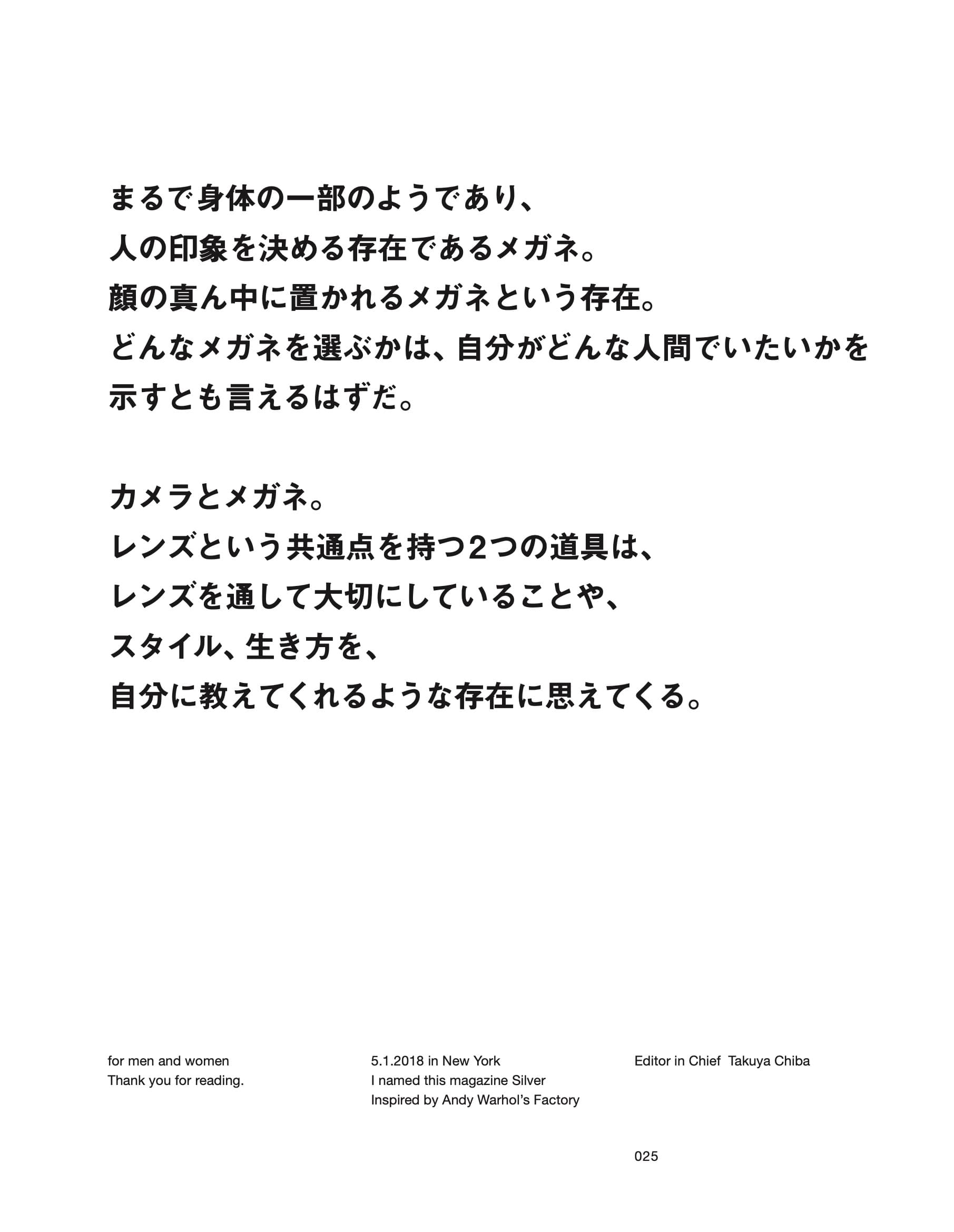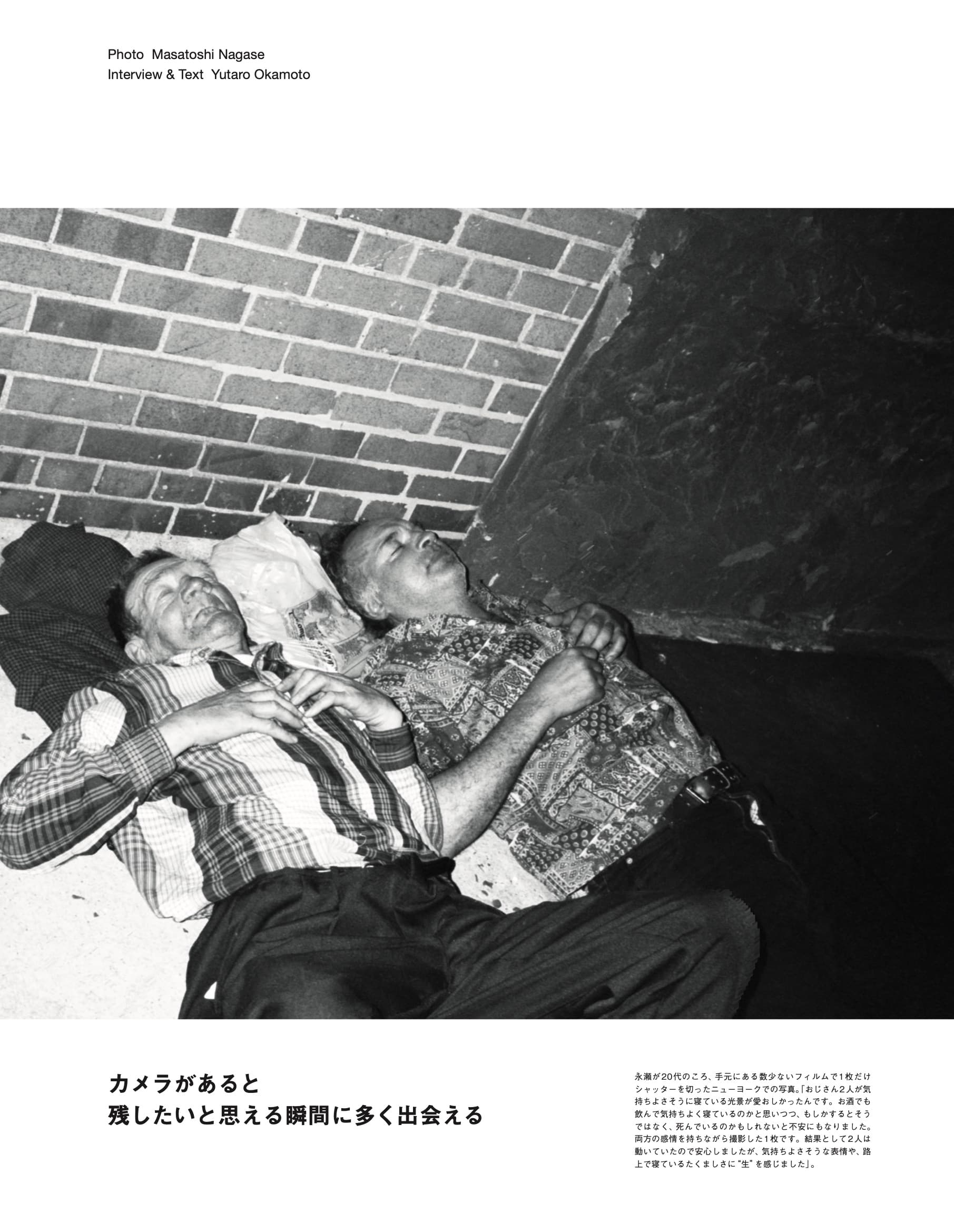Products for Feelin’ Good by Yataro Matsuura
松浦弥太郎が大切にする 立花英久による塑像

松浦弥太郎
憂いを帯びた静かな存在感を放つ一体の塑像(そぞう)。塑像とは粘土を素材にして形作られた立体造形のことをいう。松浦弥太郎は、この立花英久による塑像を、自宅の目につく場所に置き、日々の暮らしの一部としてともに過ごしている。
松浦がこの塑像に出会ったのは2009年の頃。立花英久の弟であり、アートディレクターの立花文穂と交流のあった松浦は、コラム本の装丁やアパレルブランドのカタログ制作などのデザインを通じ、互いに尊敬し合う関係を築いていた。ある日、文穂から「兄が個展を開きます」と案内状が届く。その案内に掲載されていたのが、英久の初個展“さよならさよならきみの僕”に出品された塑像であり、後に松浦が手に入れることになる作品だった。

「案内状を見た瞬間、衝撃を受けました。女性の塑像がただ立ち尽くしているだけの写真。それなのに強烈な魅力があって、どうしても手に入れたいと思ったんです。展覧会初日、誰よりも早くギャラリーへ駆けつけました」。
ギャラリーに並んだ何体かの塑像のうち、その作品は中央に置かれていた。松浦は迷うことなく、購入を申し出たという。
「立花英久さんはこれまでに、たくさんの展覧会をしてきました。この最初の作品はまだ不完全であり、試行錯誤や戸惑いの中で作られたもの。でも、その不完全さにこそ純粋さを感じたのです。初期作品というものは本人の不安や不確かさ、迷いみたいなものが作品にこう滲んでいて。それが、とても人間的な温かみとなり、なぜこの塑像を作ろうとしたのか、その動機までも伝わってくる。英久さんは女性をモチーフにしていますが、ぼくが思うに、彼にとっての人間というのは女性なんですよね。それは例えば、母親かもしれないし、もっと大きな存在なのかもしれない。人間の象徴のようにも感じます。作品は“人間とは何か”という問いを見るものに問いかけている感じがするんです」。
松浦がこの塑像を購入してから16年。この塑像は今も日常の風景の一部だ。絵画や写真、ポスターなど、幅広くアートを収集してきたが、こういった立体的な作品はほとんど持っていないという。なぜなら、この塑像があればほかに必要ないと思えるからだ。
「この塑像はどんな人なのか。女の人のように見えて、実は男の人かもしれない。若くも見えるし、そうでないとも見える。見るたびに印象が変わるんです。そうした“決めつけられない存在”こそ、作品として大きな魅力だと思います。こんなことを言うと立花英久さんは心外かもしれないけれど、僕がこの作品から感じるのは、塑像を作る動機が“苦しみ”にあるのではないかということ。苦しみの中で光を探す行為として、彼は塑像を作ったのではないか。その苦しみをいかに受け止めること自体が人間性でもあり、人間の美なのだと、この作品は教えてくれるんです。綺麗、素敵といった表層的な評価ではなく、もっと本質的な美しさをこの作品は示してくれていると僕は思うんです。だからこそ、これが身近にあることというのは、非常に自分自身が励まされていて、力をもらえるような気がするんです。アートが言葉を発せずとも、そばにあるだけで支えになり、エネルギーを与えてくれる。それが人とアートの理想的な関係だと思うんです。そして、それはまさに、僕と立花英久さんの塑像との間に存在しているんです」。
松浦弥太郎
1965年、東京都生まれ。エッセイスト、クリエイティブディレクター。2006年から2015年まで「暮しの手帖」編集長を務める。現在は多くの企業のアドバイザーも行う。
| Photo Kengo Shimizu | Interview & Text Takayasu Yamada |