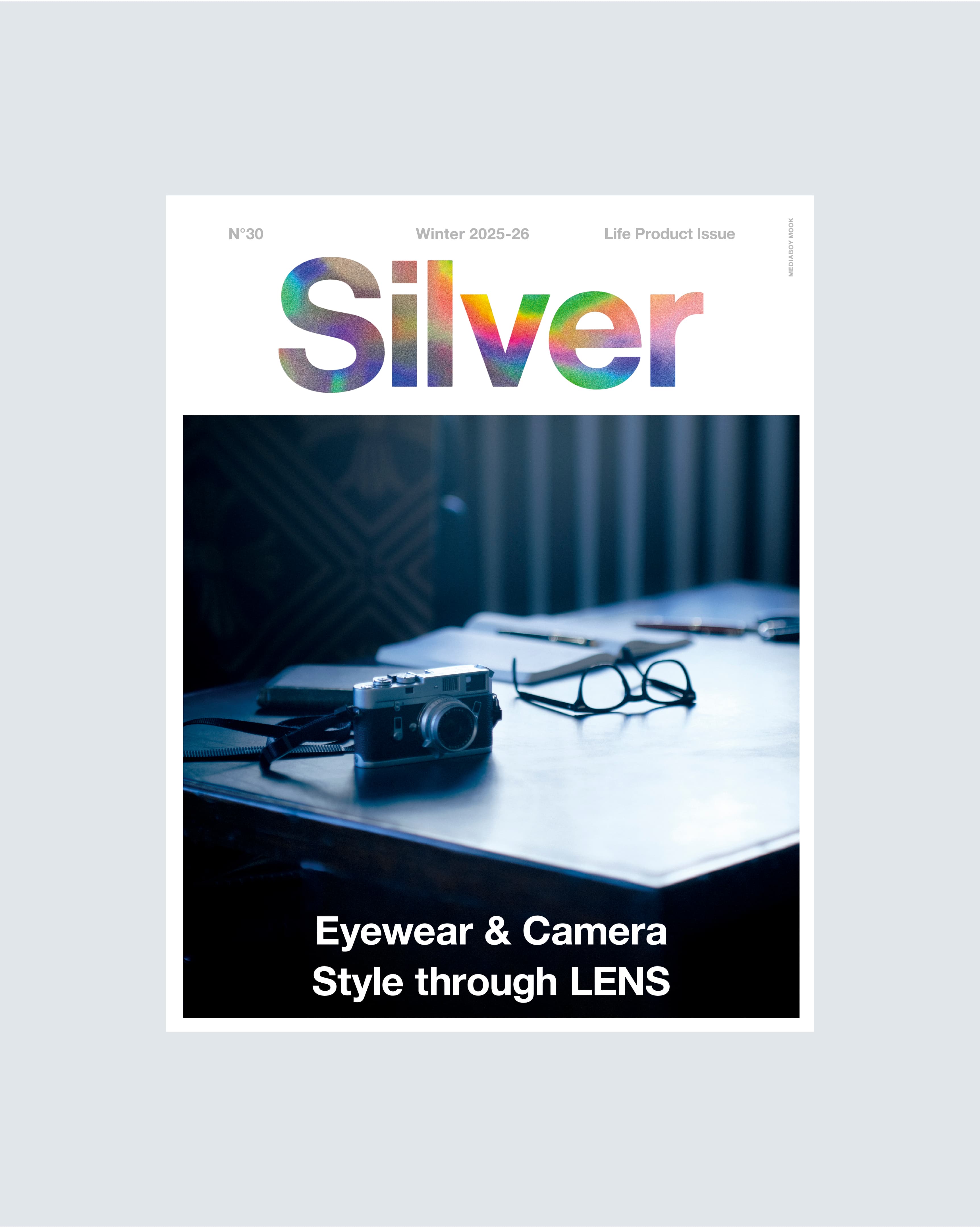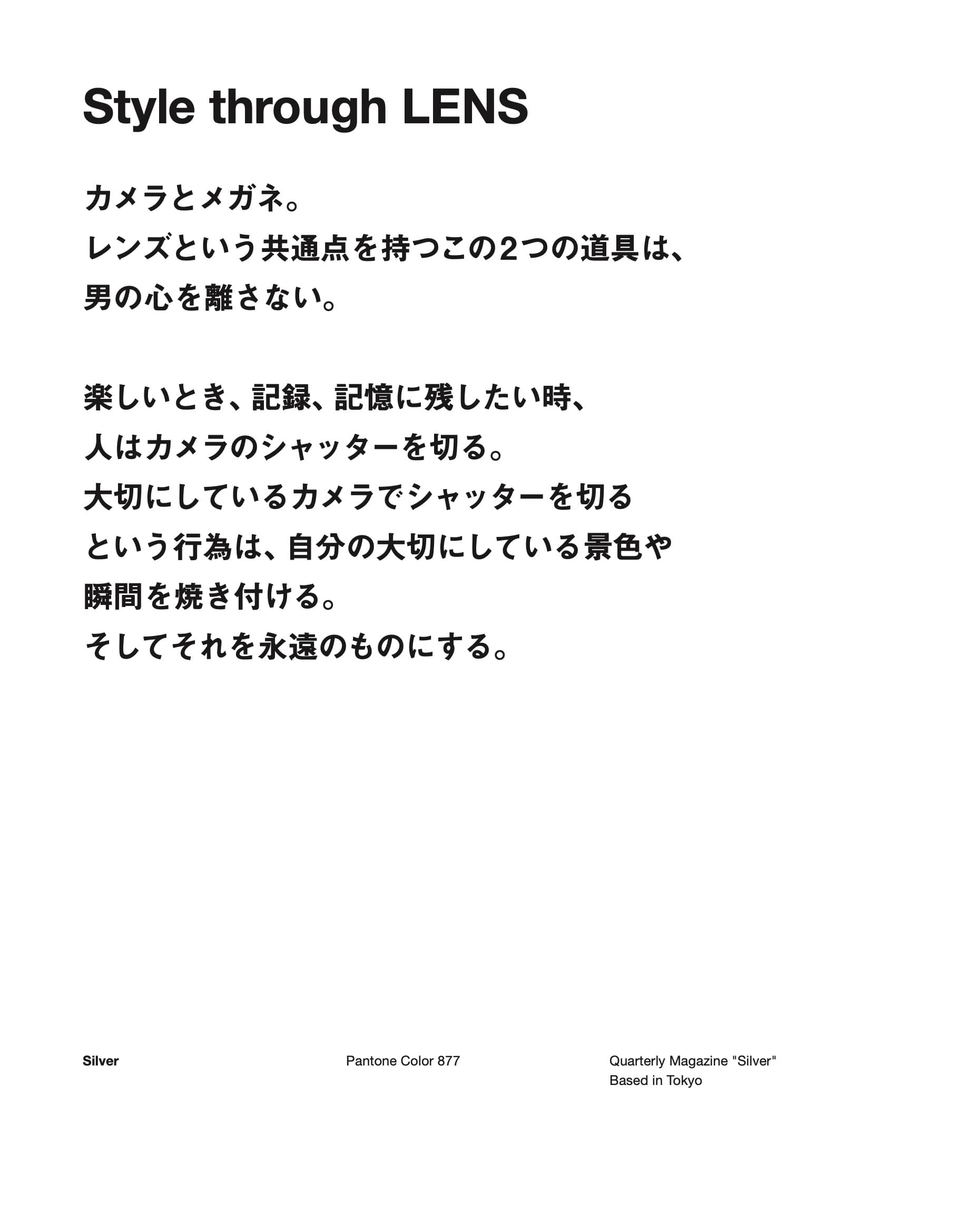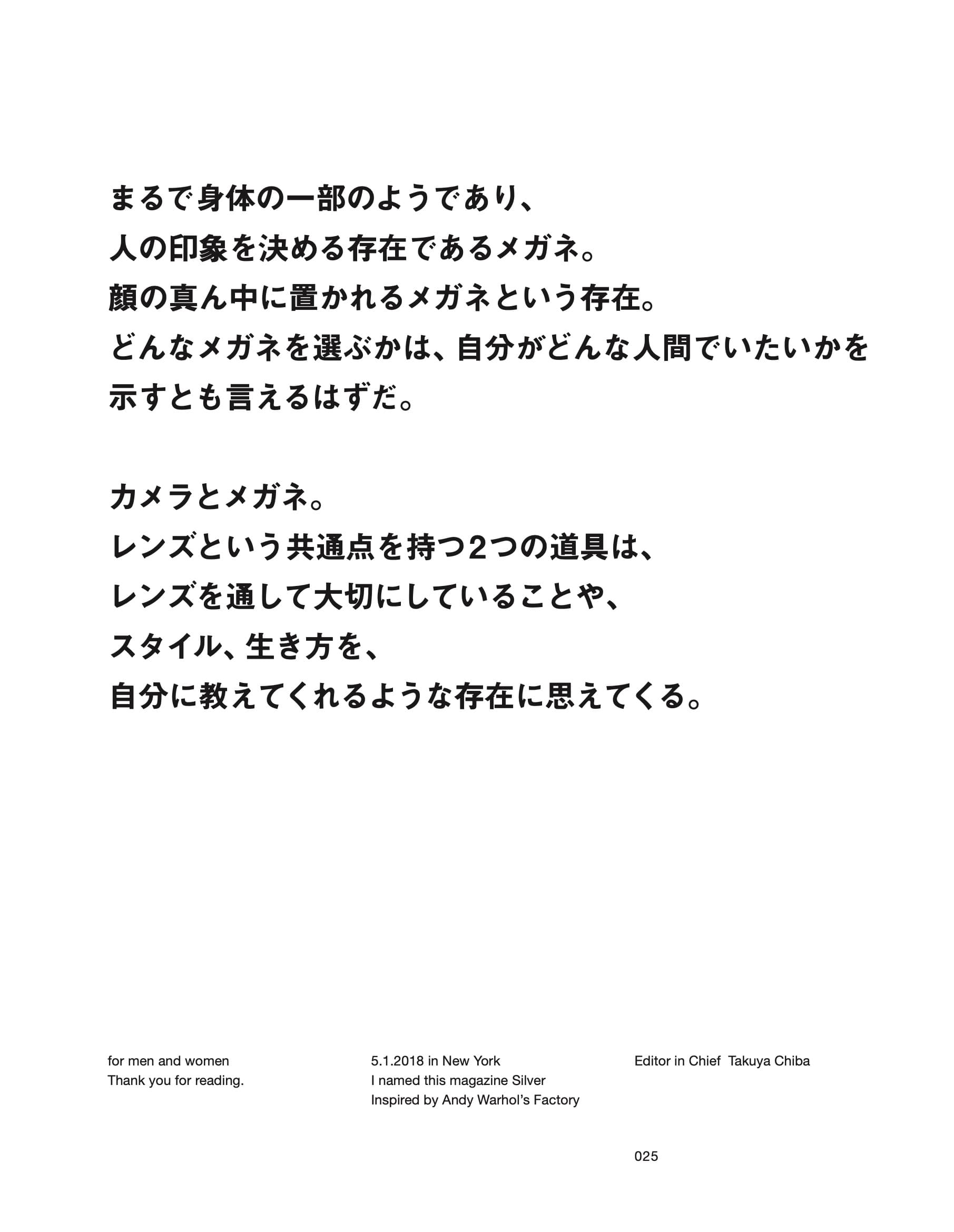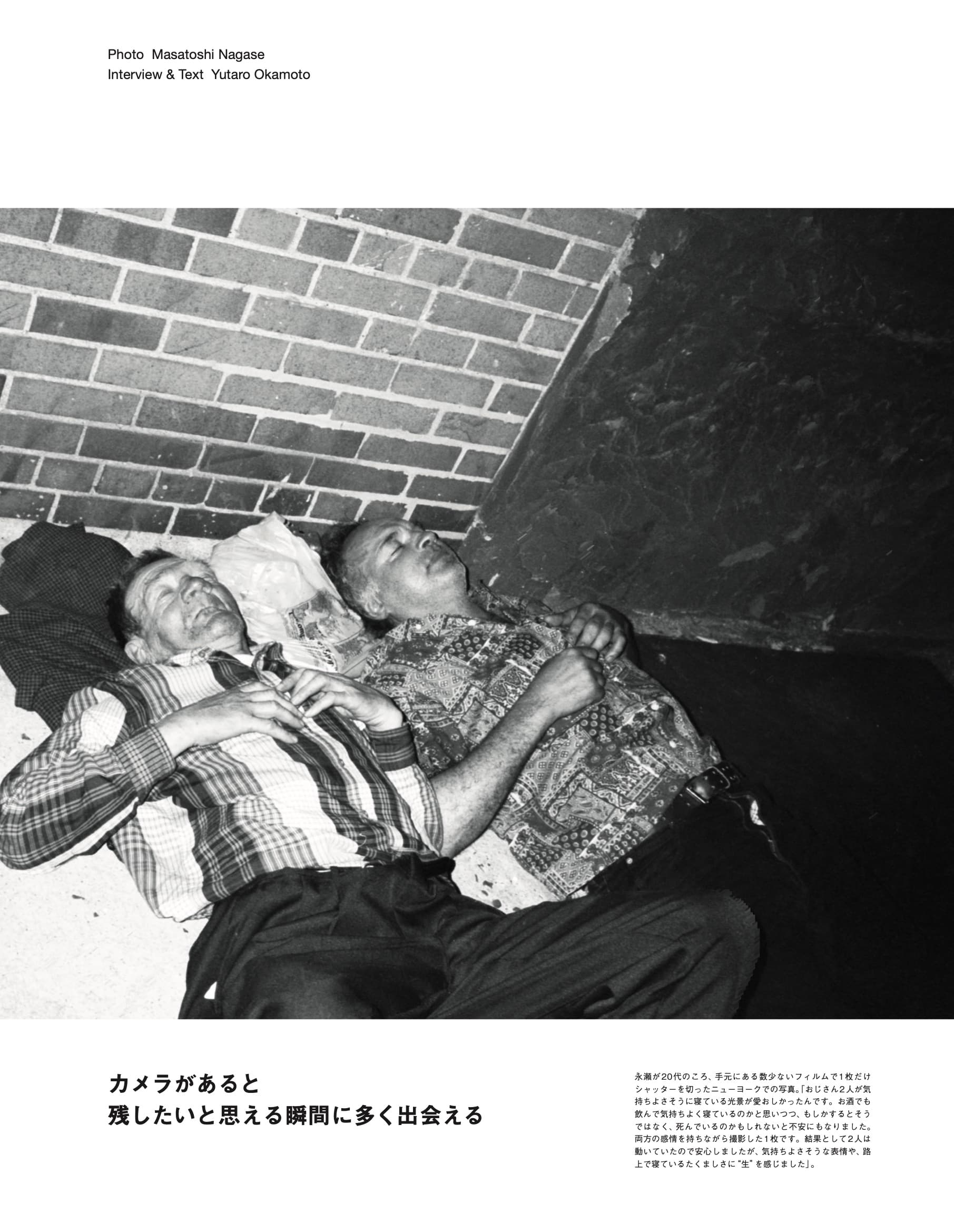ART & CRAFTS Woodwork TOSHIAKI UMEMOTO
木工作家 梅本敏明が作る 丸太を削り出したスツールや花器

黒く、ずっしりと無言の存在感を放つ物体。よくよくテクスチャーに目を凝らすと、木目や割れの具合から木でできていることがわかる。この木工作品は、県土の8割を木が占める紀州の国・和歌山県を拠点に活動する梅本敏明が作ったスツールと花器だ。本連載のナビゲーターである南貴之は、梅本の作品との出会いをこう語る「。最初は写真で作品を見たのですが、一体これは何なのか理解できなくて。重いのか軽いのか、ペンキで塗っているのか、木自体が黒いのか。いずれにせよ、塊としての迫力や空間に“いる”という力が凄まじくて。
でも、どこか間も持ち合わせていて余裕があり、不思議と空間に調和しているんです。プリミティブな作りなのにモダンさもあり、それが間となってかっこいいのだと思います。だからあまり用途は考えず、彫刻作品のようにそのままポンと部屋に置いてあります。初めて彼の個展に行った時は、一瞬で『この人が梅本さんだ』と気付きました。無骨ながらに柔らかさや優しさを兼ね備えた作品の雰囲気が彼からも溢れているんです (南)」。
南は梅本と対面し、作品を実際に目にした瞬間に惚れ込んだと話す。そして南が手がける飲食店のための木工作品制作をその場で依頼したという。そんな梅本だが、木工作家として活動するまでには紆余曲折があったと話す。
「大学では建築を学びつつ、同時に美容専門学校にも通っていました。若い頃って、そういうものに憧れるじゃないですか(笑)。そのまま卒業後は美容師として働き始めましたが、自分が本当にしたかったことを28歳の頃に考え直したんです。元々建築や家具に興味があったので、知り合いの紹介から福井県の越前漆器を作る会社で働くことになりました。それが木工に関わり始めたきっかけですね。大学で学んだ建築の知識をいかし、漆器のプロダクトデザインをしていました。その会社で7年ほど働いてから独立し、今に至ります。
独立した頃は材料を買うお金もなかったので、ホームセンターで安い合板を手に入れて椅子やトレーを作り始めました。当時渋谷ヒカリエの「d47 MUSEUM」で47都道府県の工芸品を集めた展示会があり、僕の作品が和歌山県代表として選ばれたんです。それで出品していたら、コム・デ・ギャルソンの川久保玲さんがいらっしゃって、僕の作品を面白がってくださったんです。それがきっかけで彼女が手がけるドーバーストリートマーケットでも取り扱ってもらえることになり、ロンドンやニューヨークの店舗にもトレーを送るようになりました。合板は素材が小さく薄いので、それをどう積み上げて大きくしていくかという足し算の考え方です。素材をどう使えば思い描いている立体物に近づけるかという、デザインや建築に近い感覚があります。でも今回の作品は丸太を素材とし、そこから削っていく引き算の考え方です。丸太は中身が詰まっているので、自由な形に削り出しやすいし、幾何学的な形にしなくても作品として成立します。だから、より身体的で感覚的な表現ができるんです。
例えば今回の花器だと、丸を目指して削っていきますが、フリーハンドなのでどうしてもまん丸には仕上げられない。だから形の歪みや刃物の跡はわざと残して、それを素材の力強さとして活かしたいと思いました。丸太のサイズ感や節、木目などの個性に向き合い、それをどう削り出して活かすかをいつも考えます。自分がどうしたいかではなく、丸太の中に眠っている形を削りだす感覚です。木材の色味や節目をいかすために、塗料は漆や柿渋、ベンガラなどを相性に合わせて使い分けます。今回の作品はどちらも和歌山県の紀伊山地で育てられた杉の木を使っていて、塗料には漆科のカシューナッツの殻から作られるカシューオイルを使っています。それを何度も染み込ませるように塗るので、木のテクスチャーが深みとして活かされます。技術を売るようなことはしたくなく、素材に向き合った大らかで自由な作品をこれからも生み出していきたいです (梅本)」。
自然の中にあった状態に近い素材に向き合うことでこそ、より自分の心を開いた表現ができる。それは人間の中に眠る野生の本能が目覚めることなのかもしれない。文明の発達と共に忘れ去られつつあるこの感覚こそ、言葉では表現しきれない感動を与えるものを生み出すのだ。


梅本敏明和歌山県出身。武蔵野美術大学建築学科中退後、異業種の美容師として働く。その後は越前漆器のプロダクトデザイナーに転身。独立後は木工作家として活動し、合板から丸太まで幅広い素材を扱う。
南貴之クリエイティブディレクターとしてファッションから空間まで多岐にディレクションする。自身がプロデュースする小川珈琲堺町錦店では、オープンに合わせて特注した梅本の花器を置いている。
| Select Takayuki Minami | Photo Masayuki Nakaya | Interview & Text Yutaro Okamoto |